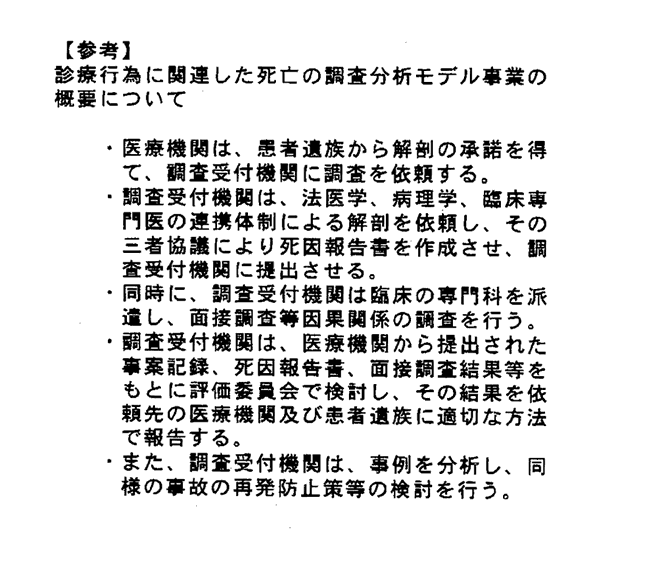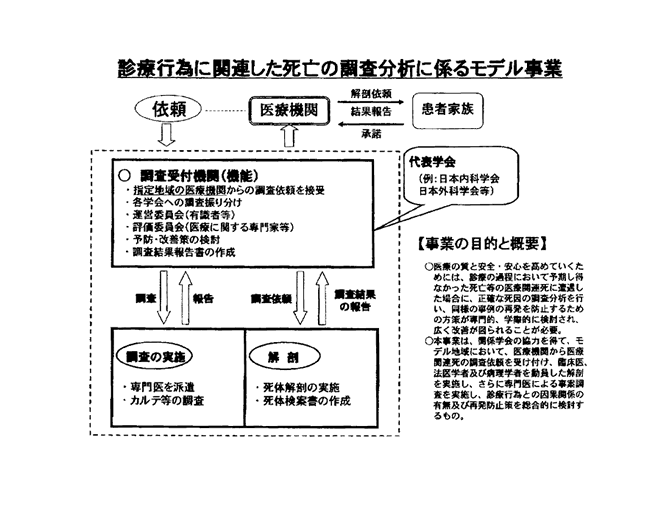東京都千代田区神田須田町2-17
神田INビル6階
TEL 03-6206-9070
FAX 03-6206-9077
mail:jsp.office@pathology.or.jp
HOME > 新着情報 > 続、最近の異状死(医療関連死)問題の動向について
| 続、最近の異状死(医療関連死)問題の動向について |
理事長 森 茂郎
四学会合同ワーキンググループ病理側委員 根本 則道
四学会合同ワーキンググループ病理側委員 黒田 誠
いわゆる異状死(医療関連死)を一律に警察へ届ける、という法律解釈が臨床各科に混乱と戸惑いをあたえていることへの対応として、厚労省が従 来の方式と異った仕組み、具体的には第三者機関への届け出制度を考えています(本年8月30日付けで本HPにおいて既報)。今秋、この新しい仕組み(モデ ル事業)を設計、試行するための班会議が厚労省から立ち上がり、構想が急速に具体化しております。前回の病理学会HP記事の続編として、ここに現時点での 進捗状況を報告します。
1.8月末以降の経過
(1)8月に、厚労省から理事長に対し、モデル事業への協力依頼と挨拶がありました。私どもはこれを肯定的に受け止め、病理学会としての見解をまとめ、厚労省に伝えました。(前報参照)。
(2)10月に、モデル事業を準備するための厚労省の会議(医療関連死モデル事業の厚生科学研究班)が立ち上げられました。メンバーは厚労省の 指名によるもので、分担研究者: 池田康夫、山口徹;研究協力者:稲葉一人、黒田誠、吉田謙一、宮田哲郎他、であります。病理からは黒田誠理事(病理業務 委員長)が指名されました。
(3)この班の役割は、モデル事業を行う地域、人員を選考し、同時に事業内容を詰めてゆく、というもので、事業内容については一枚の図と、約300文字の説明文が届けられました(本記事に添付)。
(4)11月には、班会議は法医学が先行した形で、事業に協力してくれるモデル地域を決める作業に入りました。班と各法医学講座等の折衝の結 果、以下の大学/施設の法医学の長が、参加可能と返事したとのことであります。ちなみに対応 可能と返事した大学医学部の法医学教室などは、札幌医大、東京都数施設、神奈川(詳細未定?)、新潟大、大阪大、兵庫の監察チーム、九州大です。
(5)次いで、班会議のスタッフより黒田教授を介して学会に、これらの法医学者とチームを組んでモデル事業に参加できそうな病理施設を見つけて ほしい、と要請がありました。そこで私どもはこれらの地域を含む支部長に依頼して、その地域の主な病理に事業への参加の可能性を打診いたしました。その結 果、以下の病理から参加可能との返事をいただきました。12月8日の第3回班会議においてこのリストを提出しました。
**********************************
厚労省モデル事業病理側協力施設(16年12月8日段階)
北海道:札幌医大、北海道大学
新潟県:新潟大学、長岡赤十字病院
東京都:日本大学、東京大学、昭和大学、慈恵医大、帝京大学、順天堂大学
神奈川県:東海大学、横浜市立大学、聖マリアンナ医大
愛知県:愛知県剖検ネット
大阪府:大阪大学、大阪市立大学
兵庫県:神戸大学、兵庫医科大学(協力予定)
福岡県:九州大学、久留米大学
****************************************
(5)今後は、班会議を中心にして実施法の詳細が詰められ、同時に各地域ごとに、参加を表明してくれた病理側協力者と法医、臨床家代表が話し合い、その地域に合った体制を作ってゆくことになっています。
2.モデル事業で何をするのか?
与えられている資料としては添付のチャートがすべてで、詰められていない部分もまだ多いのですが、およそのところは、医療関連死と考えられる症例につい て、中央的機構である調査受付機関(仮)の依頼のもとに、すでに構成されている病理、法医、臨床家チームが共同して剖検にあたり、その報告書を連名で作成 する(この経費は手当てする)。そのような経験を積み、集約することで、新しい制度を考えてゆく、というものと認識しています。剖検の試行は、来年から5 年間が予定されています。
3.本件についての病理学会の判断
I. 厚労省から学会に話があった段階で、学会の基本的立場を表明しました。要約すると:
1)基本的に医療の向上につながる重要な試みと認識し、支持、歓迎する。
2)従来の法医学領域の業務(司法解剖、行政解剖)のお手伝いではなく、我が国の医療検証システムの新構築と認識している。本事業には病理、法医が共同で当たるものであると理解している。
3)この事業に参加することが病理医に誇りとインセンテイブをあたえる形になることが必要で、これがないと、現場の病理の支援は得られない。
というものです。
II. 11月に入って試行の具体的な形が見え始めてきましたので、あらためて対応を検討し、病理学会として以下の意見書をまとめて班会議に提出しました。意見書の要旨は、
1)司法解剖、行政解剖は本試行から切り離すべきである。そうすると、残りの医療関連死の解剖には病理学の立場からの解析の比重が非常に重くなる。本試行においては病理解剖の比重が高いことが認識されることが必要である。
2)地域(都道府県など)一カ所だけが試行に参加する、ということではなく、複数の単位をも置けて、それらの輪番制で進めるべきである。
3)参加することによって病理医が誇りとインセンテイブを持てるような仕組みが必要である、という主張の再確認。というものです。この文書は黒田理事によって病理側の意見として班会議メンバーに配布され、口頭説明がなされております。
4.今後の方向と、病理の立場からの留意事項。
今後これらの地域には、試行のためのチームができる予定です。試行の期間は来年(平成17年度)から5年であり、その間にこれらの地域で発生した医療関連死の剖検は、基本的にこれらのチームによって行われることになります。
このシステムによる剖検の実施法の詳細は、班会議レベルでまだ詰まっていません。医療関連死の定義から始まり、部署として当面対応する必要のある内容の 詳細、支払われる経費、法律および警察との関係の整理、などについて班会議で論議、決定されることになります。その後、それを受けて地域に適した形に合わ せる作業があります。
該当する剖検は全国で300例程度を見込んでいるとのことですが、実際どれくらいの解剖がくるのか、ふたを開けてみなければわからない、と思います。
数年後には、今回の施行を集約し、それを全国に制度として定着させることが出来るかどうかの論議があるはずです。一方、今回の試行は条件が比較的整った地域で行われており、これを全国にそのまま当てはめることには困難も予想され、その克服が必要です。
今回の事業は、「公的支援による、医療関連死の死因解明のためのシステムを、全国レベルで確立させること」に直結する試であるととらえられます。言い換 えればこの事業は、今現在の、問題の多い一律警察届け出制度の改正、それによる医療検証制度の向上、医療に対する患者さんや社会的信頼の強化、をめざした 事業であると認識しています。これが学会として強く支援をしてゆきたい大きな理由のひとつです。
この作業は現場の病理単位の理解と積極的な協力がなくては成立しません。関係各位にはあらためてご協力をお願いいたします。また、協力をためらわせる障 害があるとすればその解明、解消につとめてゆくことが重要ですので、問題点は遠慮なくお申し越しいただきたいと思います。本件に関して不明な点、ご意見な どありましたら、私共のところまでおよせください。