〒101-0041
東京都千代田区神田須田町2-17
神田INビル6階
TEL 03-6206-9070
FAX 03-6206-9077
mail:jsp.office@pathology.or.jp
東京都千代田区神田須田町2-17
神田INビル6階
TEL 03-6206-9070
FAX 03-6206-9077
mail:jsp.office@pathology.or.jp
HOME > 市民の皆さまへ > 病理学の研究でわかること
| 病理学の研究でわかること |
日本病理学会では、学会員が行なっている学術研究活動を広く知っていただくために、宿題報告担当者による研究の解説を公開しました。病理学の研究によってどのようなことが分かり、どのように医療に活かされていくのか、その成果がどのように市民に還元される可能性があるのか、についてご理解いただけることを期待しています。
日本病理学会宿題報告とは:
日本病理学会では、病理学領域における特定の課題について卓越した業績を挙げていると判断された会員が、その課題の業績を日本病理学会総会において報告し、もって会員の病理に関する学術、医療の振興とその普及に資することを企図して「宿題報告」を設けています。
その内容としては、1)国内外の評価のある業績であること、2)断片としての学術情報ではなく、体系として受け取れる内容であること、3)演者の示す問題把握のしかた、課題の解決法、学問観などが会員にとって大いに資するものであること、を要件としています。代表的な論文の学術的評価、その領域自体のもつ重要性や将来性、応募者の学術性や適格性などを含む多面的な判断基準によって学術委員会で厳正に選考されています。
宿題報告は、明治44年(1911年)の藤浪 鑑先生による「日本住血吸虫-病理解剖的方面」に始まり、100余年の歴史の中で、古くは長与又郎先生、山極勝三郎先生、吉田富三先生など偉大な病理学の先達によって行なわれています。
>>「過去の宿題報告一覧」
日本病理学会宿題報告とは:
日本病理学会では、病理学領域における特定の課題について卓越した業績を挙げていると判断された会員が、その課題の業績を日本病理学会総会において報告し、もって会員の病理に関する学術、医療の振興とその普及に資することを企図して「宿題報告」を設けています。
その内容としては、1)国内外の評価のある業績であること、2)断片としての学術情報ではなく、体系として受け取れる内容であること、3)演者の示す問題把握のしかた、課題の解決法、学問観などが会員にとって大いに資するものであること、を要件としています。代表的な論文の学術的評価、その領域自体のもつ重要性や将来性、応募者の学術性や適格性などを含む多面的な判断基準によって学術委員会で厳正に選考されています。
宿題報告は、明治44年(1911年)の藤浪 鑑先生による「日本住血吸虫-病理解剖的方面」に始まり、100余年の歴史の中で、古くは長与又郎先生、山極勝三郎先生、吉田富三先生など偉大な病理学の先達によって行なわれています。
>>「過去の宿題報告一覧」
※宿題報告順に掲載
-
NEW
-
骨を削る破骨細胞はどのように作られているのか 北澤 荘平(愛媛大学大学院医学系研究科分子病理学講座)
 骨が健康であるためには、骨を作る骨芽細胞と骨を吸収する破骨細胞のバランスが大切です。このバランスが崩れると、高カルシウム血症、癌の骨転移、リウマチ、骨粗鬆症、骨折、骨腫瘍など、さまざまな病気が起こります。私たちは、骨の形成や破骨細胞の形成、腫瘍の進行に関わる遺伝子の働きを研究しています。この研究が、骨の病気や腫瘍の骨への浸潤、骨転移の仕組みを理解する手助けになると考えています。今回は、その研究成果をご紹介します。>>続きはこちら
骨が健康であるためには、骨を作る骨芽細胞と骨を吸収する破骨細胞のバランスが大切です。このバランスが崩れると、高カルシウム血症、癌の骨転移、リウマチ、骨粗鬆症、骨折、骨腫瘍など、さまざまな病気が起こります。私たちは、骨の形成や破骨細胞の形成、腫瘍の進行に関わる遺伝子の働きを研究しています。この研究が、骨の病気や腫瘍の骨への浸潤、骨転移の仕組みを理解する手助けになると考えています。今回は、その研究成果をご紹介します。>>続きはこちら
-
環境化学物質の発がんリスク評価:ヒトのがん予防への貢献 鰐渕 英機(大阪公立大学大学院医学研究科分子病理学)
 環境には「がん」を引き起こす物質「発がん物質」が多数存在し、その物質を同定しがんが発生する仕組み「発がんメカニズム」を解明することは、人々の健康向上に大切です。その解明を目的に動物実験を行い、生活環境に存在するヒ素や職業的にばく露する危険性がある芳香族アミンの膀胱発がん性と発がんメカニズムを解明してきました。また、新しい発がん物質を検出する研究にも取り組んでおり、それらの成果によりヒトのがん予防に貢献しております。>>続きはこちら
環境には「がん」を引き起こす物質「発がん物質」が多数存在し、その物質を同定しがんが発生する仕組み「発がんメカニズム」を解明することは、人々の健康向上に大切です。その解明を目的に動物実験を行い、生活環境に存在するヒ素や職業的にばく露する危険性がある芳香族アミンの膀胱発がん性と発がんメカニズムを解明してきました。また、新しい発がん物質を検出する研究にも取り組んでおり、それらの成果によりヒトのがん予防に貢献しております。>>続きはこちら
-
がんの微小環境から学ぶ新しい病理学 石井 源一郎 (国立がん研究センター東病院病理臨床検査科・国立がん研究センター先端医療開発センター病理臨床検査TR分野)
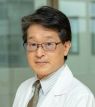 「がん」は、がん細胞のみから構成されているわけではありません。がん細胞の周囲には、多数のがん細胞ではない細胞(非がん細胞)が集まってきています。これら非がん細胞は、がん細胞との相互作用を介して特殊な微小環境を形成し、がん細胞の悪性像、あるいは薬剤感受性を修飾していることがわかってきました。従って、がんの診断・治療の進歩のためには、こうした非がん細胞の研究も重要です。ここでは、非がん細胞の代表格である線維芽細胞の研究を介してわかったことを紹介します。>>続きはこちら
「がん」は、がん細胞のみから構成されているわけではありません。がん細胞の周囲には、多数のがん細胞ではない細胞(非がん細胞)が集まってきています。これら非がん細胞は、がん細胞との相互作用を介して特殊な微小環境を形成し、がん細胞の悪性像、あるいは薬剤感受性を修飾していることがわかってきました。従って、がんの診断・治療の進歩のためには、こうした非がん細胞の研究も重要です。ここでは、非がん細胞の代表格である線維芽細胞の研究を介してわかったことを紹介します。>>続きはこちら
-
ヒトの老化や関連疾患の制御を目指す基礎老化研究 下川 功 (長崎大学生命医科学域・医学系・病理学分野)
 高齢者は、加齢に伴って身体の機能が低下し、様々な病気を発症します。ヒトの健康寿命を伸ばし、豊かな生活を送るためにも、老化の研究が重要です。我々は、老化を遅らせ、寿命が伸びる、カロリー制限マウスを用いて、老化の仕組みを解明し、高齢者の病気を抑えるための研究を進めてきました。その結果、寿命の制御に携わっているインスリン様成長因子1シグナルの下流にあるFox01、Fox03という2つの転写因子と、食欲や成長などに関係するニューロペプチドY (Npy)という神経ペプチドが、カロリー制限による寿命延長に大きく関わっていることを明らかにしました。>>続きはこちら
高齢者は、加齢に伴って身体の機能が低下し、様々な病気を発症します。ヒトの健康寿命を伸ばし、豊かな生活を送るためにも、老化の研究が重要です。我々は、老化を遅らせ、寿命が伸びる、カロリー制限マウスを用いて、老化の仕組みを解明し、高齢者の病気を抑えるための研究を進めてきました。その結果、寿命の制御に携わっているインスリン様成長因子1シグナルの下流にあるFox01、Fox03という2つの転写因子と、食欲や成長などに関係するニューロペプチドY (Npy)という神経ペプチドが、カロリー制限による寿命延長に大きく関わっていることを明らかにしました。>>続きはこちら
-
病理学研究でがんの再発の原因となるがん幹細胞を見つけ出す 田中伸哉 (北海道大学医学部腫瘍病理学教室)
 がんは日本人の死因の1位です。がん治療は日進月歩で発展していて、最近では初期治療が良く効き、一時的にがんが縮小・消失することも珍しくありません。ですが、数年後に再発することが大きな問題です。がんの再発の原因は、治療に抵抗性を示す少数のがん幹細胞(かんさいぼう)が治療後も残っているからと考えられます。私達はこれまで、がんを根本的に治すことを目指して病理学の基礎研究を行ってきました。そして最近、がん幹細胞を迅速に創り出す画期的な方法(HARP現象)を発見しました。この方法で創られたがん幹細胞を詳細に調べることにより、がんの再発を防ぐための重要な手がかりがつかめます。ここではこれまでの研究の概要と将来展望をご紹介します。>>続きはこちら
がんは日本人の死因の1位です。がん治療は日進月歩で発展していて、最近では初期治療が良く効き、一時的にがんが縮小・消失することも珍しくありません。ですが、数年後に再発することが大きな問題です。がんの再発の原因は、治療に抵抗性を示す少数のがん幹細胞(かんさいぼう)が治療後も残っているからと考えられます。私達はこれまで、がんを根本的に治すことを目指して病理学の基礎研究を行ってきました。そして最近、がん幹細胞を迅速に創り出す画期的な方法(HARP現象)を発見しました。この方法で創られたがん幹細胞を詳細に調べることにより、がんの再発を防ぐための重要な手がかりがつかめます。ここではこれまでの研究の概要と将来展望をご紹介します。>>続きはこちら
-
病理組織検体におけるエピゲノム解析からがんの個別化医療の開発へ 金井弥栄 (慶應義塾大学医学部病理学教室)
 病理組織検体における解析で、エピゲノム機構の異常が、いろいろな臓器の前がん段階から、発がんに寄与することを明らかにしました。DNAにはTCGAという4文字からなる暗号文を使って情報が書き込まれていますが、暗号文の文面そのものをかえずに、DNAに修飾をつけて情報をかえる仕組みが"エピゲノム"です。前がん段階のDNAメチル化異常はがんに受け継がれ、遺伝子からタンパク質ができる量や染色体の構造に異常を引き起こして、がんの悪性度や症例の予後に影響します。DNAメチル化バイオマーカーとDNAメチル化測定システムを企業と共同で開発して、実用化に努めています。エピゲノム情報は、患者さんおひとりおひとりに適した個別化医療に重要で、病気になる前に先回りして備える予防・先制医療実装の鍵を握ると考えられます。>>続きはこちら
病理組織検体における解析で、エピゲノム機構の異常が、いろいろな臓器の前がん段階から、発がんに寄与することを明らかにしました。DNAにはTCGAという4文字からなる暗号文を使って情報が書き込まれていますが、暗号文の文面そのものをかえずに、DNAに修飾をつけて情報をかえる仕組みが"エピゲノム"です。前がん段階のDNAメチル化異常はがんに受け継がれ、遺伝子からタンパク質ができる量や染色体の構造に異常を引き起こして、がんの悪性度や症例の予後に影響します。DNAメチル化バイオマーカーとDNAメチル化測定システムを企業と共同で開発して、実用化に努めています。エピゲノム情報は、患者さんおひとりおひとりに適した個別化医療に重要で、病気になる前に先回りして備える予防・先制医療実装の鍵を握ると考えられます。>>続きはこちら
-
分離腺管/間質を用いたオミックス解析に基づいた大腸腫瘍の発生進展過程の解明 菅井 有 (岩手医科大学病理診断学講座)
 これまでのヒトサンプルの解析は組織サンプルを丸ごと解析することが一般的でした。しかし、癌の分子解析には、調べたいターゲット細胞のみを解析することが重要になります。私たちはターゲット細胞のみを採取する方法を開発しヒトサンプルの分子解析を行なってきました。一方で分子解析を行う場合、解析対象の分子を網羅的に解析する方法が必要になります(オミックス解析と言います)。私たちの研究はこれらの2つの方法を用いて大腸癌の分子機序の解明を試みたものです。大腸癌の発生に関わる分子メカニズムなどをご紹介します。>>続きはこちら
これまでのヒトサンプルの解析は組織サンプルを丸ごと解析することが一般的でした。しかし、癌の分子解析には、調べたいターゲット細胞のみを解析することが重要になります。私たちはターゲット細胞のみを採取する方法を開発しヒトサンプルの分子解析を行なってきました。一方で分子解析を行う場合、解析対象の分子を網羅的に解析する方法が必要になります(オミックス解析と言います)。私たちの研究はこれらの2つの方法を用いて大腸癌の分子機序の解明を試みたものです。大腸癌の発生に関わる分子メカニズムなどをご紹介します。>>続きはこちら
-
心臓不整脈を可視化する ―発生のメカニズムを解明する実験病理学研究― 田中秀央 (京都府立医科大学大学院医学研究科 細胞分子機能病理学)
 心臓の興奮伝導機能の異常である不整脈はなぜ起こるのか、その解明には心臓の機能と形態とを組織・細胞レベルで解析する実験的アプローチが必要です。私たちは実験動物から摘出した心臓や心筋細胞を分離・培養した組織を用いてその興奮伝導の様子を蛍光で可視化し、さらに不整脈を生じる組織形態・機能変化を複数の方法を用いて統合的に捉えることによって、不整脈の発生メカニズムの解明に取組んできました。ここでは私たちが明らかにした不整脈の実験研究の成果と意義について紹介します。>>続きはこちら
心臓の興奮伝導機能の異常である不整脈はなぜ起こるのか、その解明には心臓の機能と形態とを組織・細胞レベルで解析する実験的アプローチが必要です。私たちは実験動物から摘出した心臓や心筋細胞を分離・培養した組織を用いてその興奮伝導の様子を蛍光で可視化し、さらに不整脈を生じる組織形態・機能変化を複数の方法を用いて統合的に捉えることによって、不整脈の発生メカニズムの解明に取組んできました。ここでは私たちが明らかにした不整脈の実験研究の成果と意義について紹介します。>>続きはこちら
-
腫瘍の多様性を担う因子の解析:病理検体から学ぶこと 森井英一 (大阪大学大学院医学系研究科 病態病理学・病理診断科)
 私たちのからだは多彩な細胞で形作られています。がんをはじめとする腫瘍も、同様に多彩な細胞からなっています。腫瘍は、原則として一種類の細胞が際限なく増えている状態なのですが、増えた細胞のかたちや役割は一つとは限りません。例えば、腫瘍の中には治療により死滅しやすい細胞と、治療に抵抗する細胞が同時に混在しています。従って、適切な治療を行っても、治療に抵抗する細胞が残っていると、再発や転移を起こすことがあります。ここでは、治療に抵抗する細胞を病理検体で可視化し、その成り立ちを解析する病理学的研究の成果を紹介します。>>続きはこちら
私たちのからだは多彩な細胞で形作られています。がんをはじめとする腫瘍も、同様に多彩な細胞からなっています。腫瘍は、原則として一種類の細胞が際限なく増えている状態なのですが、増えた細胞のかたちや役割は一つとは限りません。例えば、腫瘍の中には治療により死滅しやすい細胞と、治療に抵抗する細胞が同時に混在しています。従って、適切な治療を行っても、治療に抵抗する細胞が残っていると、再発や転移を起こすことがあります。ここでは、治療に抵抗する細胞を病理検体で可視化し、その成り立ちを解析する病理学的研究の成果を紹介します。>>続きはこちら
-
遺伝子改変ウサギモデルによる粥状動脈硬化の分子病態機構の究明 範江林 (山梨大学大学院総合研究部医学域基礎医学系分子病理学講座)
 現在、我が国において、心筋梗塞や脳卒中といった血管の病気が死因の約30%を占めています。その原因となる動脈硬化は加齢に伴い進行するため、人口の高齢化が加速する中で、医学領域は当然のことながら、国民の生活や社会構造にも大きな影響を及ぼしかねません。そこで、動脈硬化がどのように発生し、更に進展(進行)していくかを解明するうえで、新たな治療法及び予防法を確立することが求められています。動脈硬化のメカニズム解明の方法の一つとして、ヒト動脈硬化の病態を忠実に再現できる(ヒトの動脈硬化と同じ病気を引き起こす)実験動物を開発することは言うまでもなく肝心なことです。これまでに我々の取り組んできた新しい遺伝子改変ウサギを用いることにより、明らかとなった研究成果を紹介します。>>続きはこちら
現在、我が国において、心筋梗塞や脳卒中といった血管の病気が死因の約30%を占めています。その原因となる動脈硬化は加齢に伴い進行するため、人口の高齢化が加速する中で、医学領域は当然のことながら、国民の生活や社会構造にも大きな影響を及ぼしかねません。そこで、動脈硬化がどのように発生し、更に進展(進行)していくかを解明するうえで、新たな治療法及び予防法を確立することが求められています。動脈硬化のメカニズム解明の方法の一つとして、ヒト動脈硬化の病態を忠実に再現できる(ヒトの動脈硬化と同じ病気を引き起こす)実験動物を開発することは言うまでもなく肝心なことです。これまでに我々の取り組んできた新しい遺伝子改変ウサギを用いることにより、明らかとなった研究成果を紹介します。>>続きはこちら
-
血液脳関門という側面から挑む難治性神経疾患の病態解明と難治性克服 池田栄二 (山口大学大学院医学系研究科病理形態学講座)
 脳・脊髄・網膜などの神経組織にある血管は、血液と神経組織との間の物質移動を厳重に制限・管理する機能(血液脳関門機能といいます)を有しており、'閉じた状態'にある血液脳関門により神経組織が正常に機能するために最適な環境が維持されています。そして、この我々の身体が正常に機能するために重要な血液脳関門機能は、神経疾患(神経組織の病気)の成り立ちと治療に大きく関わっています。そこで我々は、血液脳関門機能を調節している責任分子を特定し、それらを標的として血液脳関門機能を人為的に制御('閉じた状態'⇔'開いた状態')する手法を確立することにより、いまだ有用な治療法がなく治りにくい神経疾患を克服すべく研究を進めています。>>続きはこちら
脳・脊髄・網膜などの神経組織にある血管は、血液と神経組織との間の物質移動を厳重に制限・管理する機能(血液脳関門機能といいます)を有しており、'閉じた状態'にある血液脳関門により神経組織が正常に機能するために最適な環境が維持されています。そして、この我々の身体が正常に機能するために重要な血液脳関門機能は、神経疾患(神経組織の病気)の成り立ちと治療に大きく関わっています。そこで我々は、血液脳関門機能を調節している責任分子を特定し、それらを標的として血液脳関門機能を人為的に制御('閉じた状態'⇔'開いた状態')する手法を確立することにより、いまだ有用な治療法がなく治りにくい神経疾患を克服すべく研究を進めています。>>続きはこちら
-
最強の肺がん:小細胞肺がんを神経分化から解明する 伊藤隆明 (熊本大学・熊本保健科学大学 )
 肺がんのタイプの一つである小細胞肺がんは、他のタイプに比べて、より悪性で、治療も困難です。この肺がんは、神経の性格(専門用語では神経内分泌分化と呼びます)を持つユニークな特徴があります。私たちは、この神経内分泌分化は治療の有効性と関係があり、治療が効かなくなる時は、神経内分泌分化も失われていることを明らかにしてきました。さらに、患者さんの腫瘍組織内で、これらの状態の細胞が混じりあっていると考えました。私たちは、このような小細胞肺がんの進行と神経内分泌分化状態の混じりあいの具合を、病理学の研究方法を使って明らかにし、難病である小細胞がんの克服に貢献したいと考えています。>>続きはこちら
肺がんのタイプの一つである小細胞肺がんは、他のタイプに比べて、より悪性で、治療も困難です。この肺がんは、神経の性格(専門用語では神経内分泌分化と呼びます)を持つユニークな特徴があります。私たちは、この神経内分泌分化は治療の有効性と関係があり、治療が効かなくなる時は、神経内分泌分化も失われていることを明らかにしてきました。さらに、患者さんの腫瘍組織内で、これらの状態の細胞が混じりあっていると考えました。私たちは、このような小細胞肺がんの進行と神経内分泌分化状態の混じりあいの具合を、病理学の研究方法を使って明らかにし、難病である小細胞がんの克服に貢献したいと考えています。>>続きはこちら
-
唾液腺障害の病理学研究:口腔乾燥症(ドライマウス)の原因究明と治療法の開発を目指して 斎藤一郎 (鶴見大学歯学部病理学講座)
 ドライマウスは厚労省から難病指定されているシェーグレン症候群の他に、様々な原因によって生じることが示されており、糖尿病における脱水や、腎不全患者に行われている透析行為でも重篤な症状として現れます。更年期の女性ホルモンの低下による全身の乾燥症状や、大半の唾液腺が筋肉に裏打ちされていることから口腔周囲の筋力の低下によるもの、さらには唾液腺が自律神経支配を受けていることからストレス社会を反映した症例もあります。特に薬剤の副作用によるドライマウスは深刻であり、日本の薬剤の服用量の多さも本症の背景にあります。ここでは、これまで病理学研究として行ってきたシェーグレン症候群を含めたドライマウスの成立機序の検討や治療法開発の現状について紹介します。>>続きはこちら
ドライマウスは厚労省から難病指定されているシェーグレン症候群の他に、様々な原因によって生じることが示されており、糖尿病における脱水や、腎不全患者に行われている透析行為でも重篤な症状として現れます。更年期の女性ホルモンの低下による全身の乾燥症状や、大半の唾液腺が筋肉に裏打ちされていることから口腔周囲の筋力の低下によるもの、さらには唾液腺が自律神経支配を受けていることからストレス社会を反映した症例もあります。特に薬剤の副作用によるドライマウスは深刻であり、日本の薬剤の服用量の多さも本症の背景にあります。ここでは、これまで病理学研究として行ってきたシェーグレン症候群を含めたドライマウスの成立機序の検討や治療法開発の現状について紹介します。>>続きはこちら
-
肝臓の細胞社会病理学:肝疾患における細胞の異常な振る舞いを明らかにする 西川祐司 (旭川医科大学・病理学講座・腫瘍病理分野)
 肝臓の機能は全体の70%を占める肝細胞が主に担っていますが、肝疾患においては、肝細胞だけでなく、胆汁を流す胆管構造を作る胆管上皮細胞、さらにこれらを支える種々の非上皮細胞が異常をきたします。肝疾患、特に肝硬変や肝癌の成り立ちを考える上では、肝臓を構成する細胞全体の相互作用を把握することが大切です。私たちはヒト肝疾患の未解明の課題をマウスやラットを用いた実験モデルで研究してきました。ここでは私たちの研究の中から、肝疾患を肝臓の上皮細胞(肝細胞、胆管上皮細胞)の分化異常と増殖異常の観点からとらえる試みを紹介します。>>続きはこちら
肝臓の機能は全体の70%を占める肝細胞が主に担っていますが、肝疾患においては、肝細胞だけでなく、胆汁を流す胆管構造を作る胆管上皮細胞、さらにこれらを支える種々の非上皮細胞が異常をきたします。肝疾患、特に肝硬変や肝癌の成り立ちを考える上では、肝臓を構成する細胞全体の相互作用を把握することが大切です。私たちはヒト肝疾患の未解明の課題をマウスやラットを用いた実験モデルで研究してきました。ここでは私たちの研究の中から、肝疾患を肝臓の上皮細胞(肝細胞、胆管上皮細胞)の分化異常と増殖異常の観点からとらえる試みを紹介します。>>続きはこちら
-
幹細胞性誘導が、がん細胞の持続的な増加をもたらす 加藤光保 (筑波大学医学医療系実験病理学)
 造血組織、表皮、粘膜上皮などの正常組織の細胞総数は、生まれる細胞と死ぬ細胞の数の動的平衡が保たれて一定の数に維持されています。私は、この機構が破綻して、がん細胞集団が持続的に細胞総数を増加し続けるようになる機序について検討し、がん細胞の一部で幹細胞の特性が獲得される幹細胞性誘導がその重要な機序であることを示しました。現在、幹細胞性誘導を標的として、再発のないがん治療を確立することを目指しています。>>続きはこちら
造血組織、表皮、粘膜上皮などの正常組織の細胞総数は、生まれる細胞と死ぬ細胞の数の動的平衡が保たれて一定の数に維持されています。私は、この機構が破綻して、がん細胞集団が持続的に細胞総数を増加し続けるようになる機序について検討し、がん細胞の一部で幹細胞の特性が獲得される幹細胞性誘導がその重要な機序であることを示しました。現在、幹細胞性誘導を標的として、再発のないがん治療を確立することを目指しています。>>続きはこちら
-
膵臓がんはどのようにして発生・進行するのか:膵臓がんの予防、診断、治療法の開発を目指して 古川徹 (東北大学大学院医学系研究科病態病理学分野)
 病理は病気の理(ことわり)を調べる学問です。難治性である膵臓がんがどのようにして発生、進行するかを病理学的に詳しく調べることで膵臓がんの予防法、診断法、治療法を明らかにすることができます。これまでに、膵臓がんは多段階的に発生し、DUSP6, AURKA, SON等の異常により悪性に経過することが、また、膵管内乳頭粘液性腫瘍ではGNASの異常が特異的に関与していることが明らかとなりました。これらの情報をもとに新規の治療薬を開発することで膵臓がんの予後を改善できると考えられます。>>続きはこちら
病理は病気の理(ことわり)を調べる学問です。難治性である膵臓がんがどのようにして発生、進行するかを病理学的に詳しく調べることで膵臓がんの予防法、診断法、治療法を明らかにすることができます。これまでに、膵臓がんは多段階的に発生し、DUSP6, AURKA, SON等の異常により悪性に経過することが、また、膵管内乳頭粘液性腫瘍ではGNASの異常が特異的に関与していることが明らかとなりました。これらの情報をもとに新規の治療薬を開発することで膵臓がんの予後を改善できると考えられます。>>続きはこちら
-
生きた組織を顕微鏡下に観察するライブ病理学の創生 松田道行 (京都大学大学院医学研究科 病態生物医学分野)
 近代病理学は顕微鏡で組織を観察し、病気を細胞の異常として理解する学問として19世紀に始まりました。組織切片にヘマトキシリン・エオジン染色を施し顕微鏡下に観察する手法は現在も病理学の基本です。ここに今、革命的な研究手法が導入されています。蛍光バイオセンサーを導入した動物を二光子顕微鏡下に観察することで、分子活性を生きた組織でビデオ画像化することが可能になったのです。>>続きはこちら
近代病理学は顕微鏡で組織を観察し、病気を細胞の異常として理解する学問として19世紀に始まりました。組織切片にヘマトキシリン・エオジン染色を施し顕微鏡下に観察する手法は現在も病理学の基本です。ここに今、革命的な研究手法が導入されています。蛍光バイオセンサーを導入した動物を二光子顕微鏡下に観察することで、分子活性を生きた組織でビデオ画像化することが可能になったのです。>>続きはこちら
-
アテローム血栓症の成り立ちと予防・治療へのアプローチ 浅田祐士郎 (宮崎大学医学部病理学講座 構造機能病態学分野)
 わが国ではライフスタイルの欧米化や高齢化に伴い、心筋梗塞や脳梗塞に代表される心血管病の発症率が年々増加しています。これらの多くは、動脈硬化巣が破綻し、そこに血栓が形成されることで発症します。このためアテローム(動脈硬化)血栓症と総称されています。アテローム血栓症は、わが国の死因の約4分の1を占める重要な疾患で、その成り立ちの解明と、より効果的な予防・治療法の確立が求められています。私たちは血栓が形成される機序とその予防法について研究を進めています。ここでは、動脈硬化血管における血栓の形成機序についての研究成果をご紹介します。>>続きはこちら
わが国ではライフスタイルの欧米化や高齢化に伴い、心筋梗塞や脳梗塞に代表される心血管病の発症率が年々増加しています。これらの多くは、動脈硬化巣が破綻し、そこに血栓が形成されることで発症します。このためアテローム(動脈硬化)血栓症と総称されています。アテローム血栓症は、わが国の死因の約4分の1を占める重要な疾患で、その成り立ちの解明と、より効果的な予防・治療法の確立が求められています。私たちは血栓が形成される機序とその予防法について研究を進めています。ここでは、動脈硬化血管における血栓の形成機序についての研究成果をご紹介します。>>続きはこちら
-
骨髄内の造血環境と骨髄性腫瘍 腫瘍発生における骨髄微小環境の影響 北川昌伸 (東京医科歯科大学・大学院医歯学総合研究科・包括病理学分野)
 私たちは骨髄に由来する血液細胞の腫瘍を研究対象として、骨髄の場で機能している様々な細胞群や分子群に注目して腫瘍発生の仕組みを明らかにするための基礎的研究を行っています。ここではとくに腫瘍細胞と骨髄の間質細胞の相互作用に注目した取り組みについてご紹介したいと思います。>>続きはこちら
私たちは骨髄に由来する血液細胞の腫瘍を研究対象として、骨髄の場で機能している様々な細胞群や分子群に注目して腫瘍発生の仕組みを明らかにするための基礎的研究を行っています。ここではとくに腫瘍細胞と骨髄の間質細胞の相互作用に注目した取り組みについてご紹介したいと思います。>>続きはこちら
-
希少難病の克服を目指して 内木宏延 (福井大学医学部 分子病理学)
 アミロイドーシスという病気は、普段血中を巡り様々な機能を担う蛋白質が、何かの拍子にアミロイド線維を形成し、体中の組織に蓄積する病気です。私たちの研究室では、正常な構造をした蛋白質が、どの様なきっかけでアミロイド線維を形成するのかを、試験管の中で精密に調べてきました。アミロイドーシスという病気の起こる仕組みが、この様に分子のレベルで明らかになることにより、今世紀に入るとアミロイド線維の形成を抑制する治療薬が開発され、もはやアミロイドーシスは不治の病ではなくなりつつあります。ここでは私たちの研究の歴史、今後の方向性について紹介します。>>続きはこちら
アミロイドーシスという病気は、普段血中を巡り様々な機能を担う蛋白質が、何かの拍子にアミロイド線維を形成し、体中の組織に蓄積する病気です。私たちの研究室では、正常な構造をした蛋白質が、どの様なきっかけでアミロイド線維を形成するのかを、試験管の中で精密に調べてきました。アミロイドーシスという病気の起こる仕組みが、この様に分子のレベルで明らかになることにより、今世紀に入るとアミロイド線維の形成を抑制する治療薬が開発され、もはやアミロイドーシスは不治の病ではなくなりつつあります。ここでは私たちの研究の歴史、今後の方向性について紹介します。>>続きはこちら
-
急激に増加している濾胞性リンパ腫に新たな病型を確立した 吉野正 (岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 病理学(第二/腫瘍)講座)
 リンパ腫は血液がんの一種ですが、約40年間に6倍程度増加し、現在では年間3万人以上の方が発病されています。濾胞性リンパ腫は同じ期間で約24倍になっており、年間6000人程度の患者さんがあります。診断時全身に拡がっている方が多いのですが、そのような患者さんでも抗癌剤療法が必要とされない場合がかなりあります。抗癌剤療法をするとよく反応するのですが、再発する確率が非常に高い疾患です。約9割の患者さんは長期生存されます。われわれはその濾胞性リンパ腫が十二指腸に好発することを見出し、2017年のWHO分類で「十二指腸型」という病型が認められました。>>続きはこちら
リンパ腫は血液がんの一種ですが、約40年間に6倍程度増加し、現在では年間3万人以上の方が発病されています。濾胞性リンパ腫は同じ期間で約24倍になっており、年間6000人程度の患者さんがあります。診断時全身に拡がっている方が多いのですが、そのような患者さんでも抗癌剤療法が必要とされない場合がかなりあります。抗癌剤療法をするとよく反応するのですが、再発する確率が非常に高い疾患です。約9割の患者さんは長期生存されます。われわれはその濾胞性リンパ腫が十二指腸に好発することを見出し、2017年のWHO分類で「十二指腸型」という病型が認められました。>>続きはこちら
-
癌細胞と間質細胞の相互作用が病的組織としての癌をかたちづくる 横崎宏 (神戸大学大学院医学研究科 病理学講座病理学分野)
 癌は癌細胞のみから出来上がっているのではありません。癌細胞の周囲には線維芽細胞やマクロファージ、細胞外基質、血管などの間質成分が存在し、これらの有機的集合体として癌という病的組織が成立しているのです。「組織としての癌」を理解するために行ってきた癌細胞と間質細胞の相互作用について、胃癌では線維芽細胞・骨髄由来間葉系幹細胞、食道癌ではマクロファージに注目して解析した結果とそれらの病理学的意義について紹介します。>>続きはこちら
癌は癌細胞のみから出来上がっているのではありません。癌細胞の周囲には線維芽細胞やマクロファージ、細胞外基質、血管などの間質成分が存在し、これらの有機的集合体として癌という病的組織が成立しているのです。「組織としての癌」を理解するために行ってきた癌細胞と間質細胞の相互作用について、胃癌では線維芽細胞・骨髄由来間葉系幹細胞、食道癌ではマクロファージに注目して解析した結果とそれらの病理学的意義について紹介します。>>続きはこちら
-
肝がんの病理学研究:成り立ちの解明と、精密な診断法の開発に向けて 坂元亨宇 (慶應義塾大学医学部病理学 )
 手術で切除されたがんは、病理学的に観察され、がんの広がりや種類、特徴などが診断されます。同じ種類のがん、例えば肝がんを 100 例、200 例と集めて解析すると、これまで気づかなかった特徴や個性を持ったグループがあることが見えてきます。そして、その理由を明らかにすることで、肝がんの本質に迫ることができます。診断技術の進歩、分子生物学の進歩、さらには、IT 技術の進歩により、このようながんの研究は、さらに進歩すると期待されます。ここでは、肝がんの成り立ちの解明と精密な診断法の開発に向けて行ってきた病理学的研究の成果を紹介します。
>>続きはこちら
手術で切除されたがんは、病理学的に観察され、がんの広がりや種類、特徴などが診断されます。同じ種類のがん、例えば肝がんを 100 例、200 例と集めて解析すると、これまで気づかなかった特徴や個性を持ったグループがあることが見えてきます。そして、その理由を明らかにすることで、肝がんの本質に迫ることができます。診断技術の進歩、分子生物学の進歩、さらには、IT 技術の進歩により、このようながんの研究は、さらに進歩すると期待されます。ここでは、肝がんの成り立ちの解明と精密な診断法の開発に向けて行ってきた病理学的研究の成果を紹介します。
>>続きはこちら
-
上皮組織の完全性維持に関わるプロテアーゼとその制御機構を明らかにする 片岡寛章 (宮崎大学医学部病理学講座 腫瘍・再生病態学分野)
 私たちは、細胞がその周囲のプロテアーゼ活性をどのように調節し、それが発生や組織恒常性、組織の修復再生にどのように大切なのかに興味をもっています。そして特に皮膚や消化管の表面を覆う上皮組織を対象に、この調節機構とその破綻が、炎症やがんなどの病態にどのように関わっているのかを調べ、診断や治療に結び付く基盤的知識を得るための研究を行っています。ここでは、上皮組織を維持するプロテアーゼ制御機構についての、私たちの成果をご紹介します。>>続きはこちら
私たちは、細胞がその周囲のプロテアーゼ活性をどのように調節し、それが発生や組織恒常性、組織の修復再生にどのように大切なのかに興味をもっています。そして特に皮膚や消化管の表面を覆う上皮組織を対象に、この調節機構とその破綻が、炎症やがんなどの病態にどのように関わっているのかを調べ、診断や治療に結び付く基盤的知識を得るための研究を行っています。ここでは、上皮組織を維持するプロテアーゼ制御機構についての、私たちの成果をご紹介します。>>続きはこちら
-
悪性軟部腫瘍の正確な病理診断と新規治療法開発のための新たなアプローチ 小田義直 (九州大学大学院医学研究院 形態機能病理)
 私たちは、特に病理診断が困難とされています悪性軟部腫瘍の分子生物学的アプローチに基づいた正確な診断と、一歩踏み込んでテーラーメード医療に対応した分子標的治療を目指した研究を行っており、その研究成果の代表的なものをご紹介させていただきます。>>続きはこちら
私たちは、特に病理診断が困難とされています悪性軟部腫瘍の分子生物学的アプローチに基づいた正確な診断と、一歩踏み込んでテーラーメード医療に対応した分子標的治療を目指した研究を行っており、その研究成果の代表的なものをご紹介させていただきます。>>続きはこちら
-
私達の行ってきた消化管間質腫瘍 (Gastrointestinal stromal tumor, GIST) の病態解析が著効を示す分子標的治療薬の開発に帰結 廣田誠一 (兵庫医科大学 病理学・病理診断部門)
 病理学の使命は病態の解明にあります。病理診断という、医療に直結した個々の患者さんの病態を把握する役割もありますが、基礎的な研究を通して病気の本態を明らかにし、その病気を持つ多くの患者さんの診断や治療に希望を与える役割もあります。私達は、稀少な腫瘍ではありますが消化管間質腫瘍 (Gastrointestinal stromal tumor, GIST) という特殊な腫瘍の基礎的な研究を行い、GISTの大部分がc-kitやPDGFRAという遺伝子の異常によって発生することを病理学的な研究を通して明らかにしてきました。その病態解明は、その後のGISTに対する分子標的薬の開発に結びつき、現在では多くのGIST患者さんの生命予後が改善しています。>>続きはこちら
病理学の使命は病態の解明にあります。病理診断という、医療に直結した個々の患者さんの病態を把握する役割もありますが、基礎的な研究を通して病気の本態を明らかにし、その病気を持つ多くの患者さんの診断や治療に希望を与える役割もあります。私達は、稀少な腫瘍ではありますが消化管間質腫瘍 (Gastrointestinal stromal tumor, GIST) という特殊な腫瘍の基礎的な研究を行い、GISTの大部分がc-kitやPDGFRAという遺伝子の異常によって発生することを病理学的な研究を通して明らかにしてきました。その病態解明は、その後のGISTに対する分子標的薬の開発に結びつき、現在では多くのGIST患者さんの生命予後が改善しています。>>続きはこちら
-
増殖因子の研究でわかること 笹原 正清 (富山大学 医学薬学研究部 病態・病理学講座)
 細胞増殖因子と言われる一群の分子は主として細胞の増殖や分化を制御し、生体の恒常性の維持に関与しています。その中で、私たちが実施してきた血小板由来増殖因子の研究について紹介します。元来、発がんや動脈硬化症の原因となることが推定されていましたが、研究の進展により、全身の様々な臓器で多彩な役割をはたしていることが明らかとなってきました。今後の再生医療や抗腫瘍療法等の標的分子としての可能性が期待されます。>>続きはこちら
細胞増殖因子と言われる一群の分子は主として細胞の増殖や分化を制御し、生体の恒常性の維持に関与しています。その中で、私たちが実施してきた血小板由来増殖因子の研究について紹介します。元来、発がんや動脈硬化症の原因となることが推定されていましたが、研究の進展により、全身の様々な臓器で多彩な役割をはたしていることが明らかとなってきました。今後の再生医療や抗腫瘍療法等の標的分子としての可能性が期待されます。>>続きはこちら
-
過剰鉄にご用心! 献血のすすめ 豊國 伸哉 (名古屋大学大学院 医学系研究科)
 活性酸素やフリーラジカルとよばれる反応性の高い化学分子は放射線・紫外線・薬剤などにより発生しますが、実は私たちのからだで常時発生しており、その多寡を決める重要な因子は鉄です。活性酸素は両刃の刃であり、外来細菌の殺菌に役立っていますが、重要な生体分子に傷をつけ、がんなどの病気の原因にもなっています。鉄は過剰になると触媒として作用し酸化ストレスを増強するのです。ここでは、過剰鉄が発がんのリスクであり、避けた方がよいことを示す最新の研究成果についてご紹介します。>>続きはこちら
活性酸素やフリーラジカルとよばれる反応性の高い化学分子は放射線・紫外線・薬剤などにより発生しますが、実は私たちのからだで常時発生しており、その多寡を決める重要な因子は鉄です。活性酸素は両刃の刃であり、外来細菌の殺菌に役立っていますが、重要な生体分子に傷をつけ、がんなどの病気の原因にもなっています。鉄は過剰になると触媒として作用し酸化ストレスを増強するのです。ここでは、過剰鉄が発がんのリスクであり、避けた方がよいことを示す最新の研究成果についてご紹介します。>>続きはこちら
-
腫瘍微小環境におけるマクロファージの役割 -病理学から見たがん治療へのアプローチ - 竹屋 元裕 (熊本大学大学院)
 マクロファージは白血球の一種で、生体内をアメーバの様に動き回り、死細胞や変性物質を処理したり、細菌などの体外からの異物を貪食処理して、生体の恒常性維持に貢献しています。さらに、免疫担当細胞として種々の生理活性物質を産生し、多くの炎症性疾患、動脈硬化、肥満、がんなどの様々な疾患の病態形成に深く関わっています。私たちは、マクロファージに特異的に発現するスカベンジャー受容体の解析を通して、生体内におけるマクロファージの役割を研究しています。本稿では、がんの増殖に対するマクロファージの役割についてご紹介します。>>続きはこちら
マクロファージは白血球の一種で、生体内をアメーバの様に動き回り、死細胞や変性物質を処理したり、細菌などの体外からの異物を貪食処理して、生体の恒常性維持に貢献しています。さらに、免疫担当細胞として種々の生理活性物質を産生し、多くの炎症性疾患、動脈硬化、肥満、がんなどの様々な疾患の病態形成に深く関わっています。私たちは、マクロファージに特異的に発現するスカベンジャー受容体の解析を通して、生体内におけるマクロファージの役割を研究しています。本稿では、がんの増殖に対するマクロファージの役割についてご紹介します。>>続きはこちら
-
免疫応答の秘密を探る 笠原 正典 (北海道大学大学院医学研究科)
 私たちは個体の免疫応答を支配する主要組織適合遺伝子複合体を研究対象としています。これまでに、この複合体のゲノム構造や主要組織適合遺伝子複合体クラスI分子によって提示されるペプチドを産生するプロテアソームと呼ばれるタンパク質分解酵素の研究を行ってきました。ここでは、主な研究成果についてご紹介します。>>続きはこちら
私たちは個体の免疫応答を支配する主要組織適合遺伝子複合体を研究対象としています。これまでに、この複合体のゲノム構造や主要組織適合遺伝子複合体クラスI分子によって提示されるペプチドを産生するプロテアソームと呼ばれるタンパク質分解酵素の研究を行ってきました。ここでは、主な研究成果についてご紹介します。>>続きはこちら
-
放射線耐性がんの克服 福本 学 (東北大学加齢医学研究所)
 細胞の放射線に対する応答は複雑で、科学的興味が尽きません。かつての医原病であるトロトラスト誘発肝がんの発がん機構の解析を行う中から、より有効ながん治療に貢献するような放射線治療に耐性を示すがんの分子機構の解明を目指しています。>>続きはこちら
細胞の放射線に対する応答は複雑で、科学的興味が尽きません。かつての医原病であるトロトラスト誘発肝がんの発がん機構の解析を行う中から、より有効ながん治療に貢献するような放射線治療に耐性を示すがんの分子機構の解明を目指しています。>>続きはこちら
-
胃癌の発生を抑える胃粘液の糖鎖 中山 淳 (信州大学大学院)
 糖鎖は核酸、蛋白質に次ぐ「第三の生命鎖」とも呼ばれ、発生や免疫、がんなどの様々な生命現象と密接に係わっています。私たちは胃粘液に含まれているα1,4結合型N-アセチルグルコサミン含有糖鎖が二つの異なった作用機序により胃癌の発生を予防していることを明らかにしました。ここでは、その研究成果の一端をご紹介いたします。>>続きはこちら
糖鎖は核酸、蛋白質に次ぐ「第三の生命鎖」とも呼ばれ、発生や免疫、がんなどの様々な生命現象と密接に係わっています。私たちは胃粘液に含まれているα1,4結合型N-アセチルグルコサミン含有糖鎖が二つの異なった作用機序により胃癌の発生を予防していることを明らかにしました。ここでは、その研究成果の一端をご紹介いたします。>>続きはこちら
-
細胞間接着装置タイト結合はホメオスタシスを維持し治療の標的となる 澤田 典均 (札幌医科大学)
 タイト結合は,細胞と細胞の"すきま"をシールし,そのすきまを通る分子の通過を調節して生体の恒常性(ホメオスタシス)を維持します.また血管の内側を覆っている内皮細胞のタイト結合は,脳や網膜などを守っています.タイト結合機能の破綻は,下痢,黄疸,糖尿病網膜症で認められています.私たちは,タイト結合機能の調節機構を解明し,治療に応用することを目的としています.例として糖尿病網膜症を中心に紹介します.>>続きはこちら
タイト結合は,細胞と細胞の"すきま"をシールし,そのすきまを通る分子の通過を調節して生体の恒常性(ホメオスタシス)を維持します.また血管の内側を覆っている内皮細胞のタイト結合は,脳や網膜などを守っています.タイト結合機能の破綻は,下痢,黄疸,糖尿病網膜症で認められています.私たちは,タイト結合機能の調節機構を解明し,治療に応用することを目的としています.例として糖尿病網膜症を中心に紹介します.>>続きはこちら
-
がん発生のメカニズム解明に欠かせない動物モデル 中村 卓郎 (公益財団法人がん研究会がん研究所)
 分子生物学やゲノム科学の最新技術が導入され、診断法や治療法が格段に進歩したとはいえ、がんには未解明な部分が多く残されています。とりわけ早期発見や治療が困難ながんほど、その特性を理解し、発生に至るメカニズムを解明することが急がれています。ゲノム・エピゲノム解析など解析技術の革新的な進歩により、多くのがんの病態が遺伝子レベルで明らかにされつつありますが、従来から行なわれてきた動物モデルを用いた実験もいまなお重要です。また、動物モデル自体も格段に進化を遂げています。私たち(以下一人称で)発がん研究部は、遺伝子を操作あるいは改変してヒトと同じがんをマウスに発生させることにより、多くの研究成果をあげています。>>続きはこちら
分子生物学やゲノム科学の最新技術が導入され、診断法や治療法が格段に進歩したとはいえ、がんには未解明な部分が多く残されています。とりわけ早期発見や治療が困難ながんほど、その特性を理解し、発生に至るメカニズムを解明することが急がれています。ゲノム・エピゲノム解析など解析技術の革新的な進歩により、多くのがんの病態が遺伝子レベルで明らかにされつつありますが、従来から行なわれてきた動物モデルを用いた実験もいまなお重要です。また、動物モデル自体も格段に進化を遂げています。私たち(以下一人称で)発がん研究部は、遺伝子を操作あるいは改変してヒトと同じがんをマウスに発生させることにより、多くの研究成果をあげています。>>続きはこちら
-
がんの浸潤と転移のシグナルネットワークを探る 宮園 浩平 (東京大学)
 私たちは、β型トランスフォーミング増殖因子(TGF-β)というタンパク質の働きを通じてがんの浸潤や転移の分子機構を明らかにしてきました。多くのがんは上皮細胞という細胞からできていますが、TGF-βは上皮細胞ががん化していく上皮?間葉分化転換(EMT:Epithelial-Mesenchymal Transition)という現象を促進します。一方で、TGF-βはがんに侵入してくる血管の新生やがんの元となるがん幹細胞にも作用することが明らかとなっています。TG F-βは、がんの種類やそれぞれのがんの特質によってがんの進行を促進したり抑制したりすることが特徴ですが、私たちはTGF-βの働きを理解することでがんの浸潤と
私たちは、β型トランスフォーミング増殖因子(TGF-β)というタンパク質の働きを通じてがんの浸潤や転移の分子機構を明らかにしてきました。多くのがんは上皮細胞という細胞からできていますが、TGF-βは上皮細胞ががん化していく上皮?間葉分化転換(EMT:Epithelial-Mesenchymal Transition)という現象を促進します。一方で、TGF-βはがんに侵入してくる血管の新生やがんの元となるがん幹細胞にも作用することが明らかとなっています。TG F-βは、がんの種類やそれぞれのがんの特質によってがんの進行を促進したり抑制したりすることが特徴ですが、私たちはTGF-βの働きを理解することでがんの浸潤と
転移という複雑なプロセスの理解を深めることができると考え、研究を行っています。>>続きはこちら -
慢性炎症から癌が発生する:潰瘍性大腸炎‐大腸癌系の観察から新概念を導く 岡安 勲 (北里大学)
 慢性臓器炎-発癌系を提唱し、この概念を証明するために潰瘍性大腸炎-大腸発癌をモデルとして検索し、潰瘍性大腸炎から癌が発生しやすい理由として、反復ないしは持続する炎症によって大腸粘膜上皮細胞にDNA傷害が蓄積し、また癌抑制遺伝子p53の変異が早期に生じることから、癌細胞が出現するリスクが高まることがわかりました。従って、癌発生を予防するには炎症の状況を常に把握して、炎症を適切にコントロールすることが重要です。>>続きはこちら
慢性臓器炎-発癌系を提唱し、この概念を証明するために潰瘍性大腸炎-大腸発癌をモデルとして検索し、潰瘍性大腸炎から癌が発生しやすい理由として、反復ないしは持続する炎症によって大腸粘膜上皮細胞にDNA傷害が蓄積し、また癌抑制遺伝子p53の変異が早期に生じることから、癌細胞が出現するリスクが高まることがわかりました。従って、癌発生を予防するには炎症の状況を常に把握して、炎症を適切にコントロールすることが重要です。>>続きはこちら
-
「難治性の膵がんを糖タンパク質「ムチン」の高感度分析法で早期診断する」 米澤 傑 (鹿児島大学)
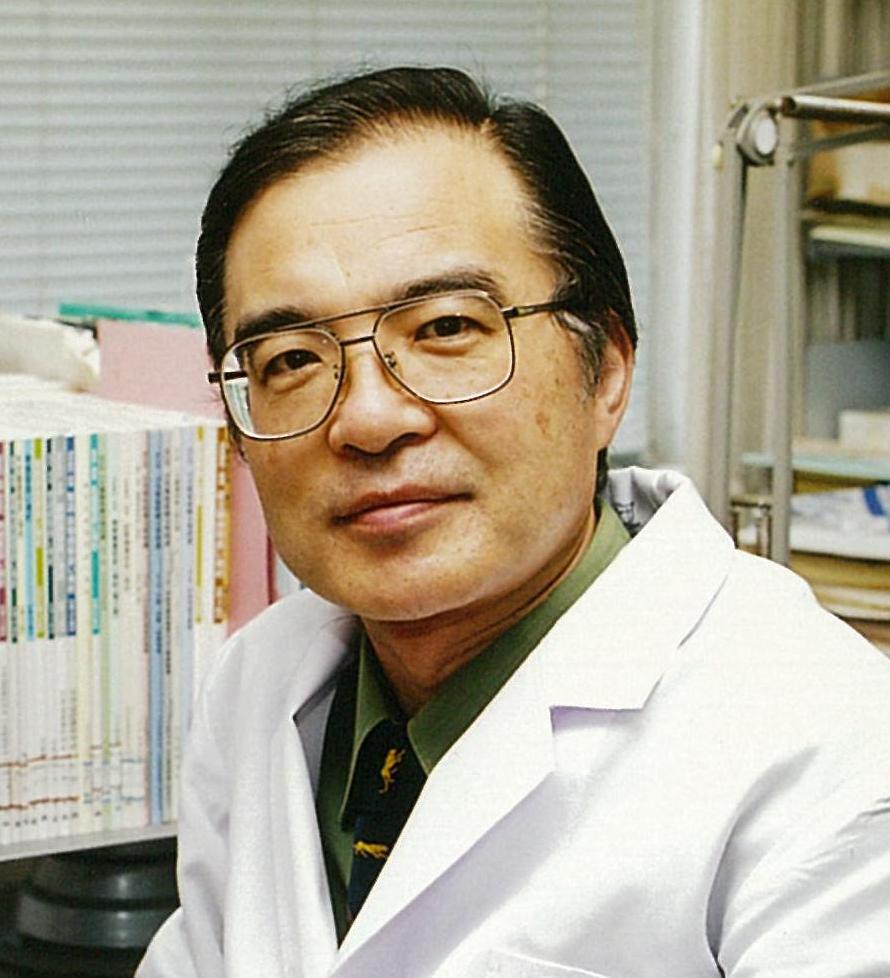 私たちは、膵がんと膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN:Intraductal papillary mucinous neoplasm)では、糖タンパク質の一種「ムチン」の発現パターンが違っていることを発見し、そのパターンの違いを、わずかな量の膵液の分析で検出できる新しい「MSE(Methylation specific electorophoresis)法」を開発しました。この新しい検出法で膵液を分析し、致死率の高い膵がんの早期発見や、他の膵腫瘍での手術の必要性の有無を含めた治療方針決定の指標を示すことを目標にしています。>>続きはこちら
私たちは、膵がんと膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN:Intraductal papillary mucinous neoplasm)では、糖タンパク質の一種「ムチン」の発現パターンが違っていることを発見し、そのパターンの違いを、わずかな量の膵液の分析で検出できる新しい「MSE(Methylation specific electorophoresis)法」を開発しました。この新しい検出法で膵液を分析し、致死率の高い膵がんの早期発見や、他の膵腫瘍での手術の必要性の有無を含めた治療方針決定の指標を示すことを目標にしています。>>続きはこちら
-
「細胞間を埋めているマトリックス・タンパク質が、難治性の慢性炎症を調節している」 上出 利光 (北海道大学遺伝子病制御研究所)
 私達の体の組織は、働きの異なる色々な細胞が集まって出来ていますが、実は、マトリックスというたんぱく質で、細胞の隙間が埋められています。お肌の張りが無くなって来たと、コラーゲンやプロテオグリカン入りの化粧品を使っておられる女性が多いと思いますが、それもマトリックス蛋白なのです。私達は、細胞を取り囲んでいるマトリックス蛋白が、色々な慢性の難治性の炎症に重要な働きをしている事を発見し、マトリックスをターゲットにしたお薬の開発に取り組んできましたので、その一端をご紹介します。>>続きはこちら
私達の体の組織は、働きの異なる色々な細胞が集まって出来ていますが、実は、マトリックスというたんぱく質で、細胞の隙間が埋められています。お肌の張りが無くなって来たと、コラーゲンやプロテオグリカン入りの化粧品を使っておられる女性が多いと思いますが、それもマトリックス蛋白なのです。私達は、細胞を取り囲んでいるマトリックス蛋白が、色々な慢性の難治性の炎症に重要な働きをしている事を発見し、マトリックスをターゲットにしたお薬の開発に取り組んできましたので、その一端をご紹介します。>>続きはこちら
-
「乳癌は何故閉経期前後の女性で多く発症するのでしょうか?」 笹野 公伸 (東北大学)
 乳癌患者さんの多くはその発症、進展過程でエストロゲンを中心とする女性ホルモンが欠かせない働きをしてます。しかしその多くは血中のエストロゲン値が低くなる閉経期前後で見つかります。この原因として乳癌では血中の副腎から分泌される弱い男性ホルモンを癌組織局所でアロマターゼと呼ばれる酵素によりエストロゲンに転換して癌細胞に作用するイントラクリノロジー(Intracrinology)と呼ばれるホルモン作用機序が関係している事が分かってきました。 そこでここではこのIntracrinologyと呼ばれる新しいホルモンの作用が女性の方々が年を重ねるとどのように関係してくるのかも含めて紹介させていただきます。>>続きはこちら
乳癌患者さんの多くはその発症、進展過程でエストロゲンを中心とする女性ホルモンが欠かせない働きをしてます。しかしその多くは血中のエストロゲン値が低くなる閉経期前後で見つかります。この原因として乳癌では血中の副腎から分泌される弱い男性ホルモンを癌組織局所でアロマターゼと呼ばれる酵素によりエストロゲンに転換して癌細胞に作用するイントラクリノロジー(Intracrinology)と呼ばれるホルモン作用機序が関係している事が分かってきました。 そこでここではこのIntracrinologyと呼ばれる新しいホルモンの作用が女性の方々が年を重ねるとどのように関係してくるのかも含めて紹介させていただきます。>>続きはこちら
-
「ウイルスとがん ―EBウイルス胃がんの研究―」 深山 正久 (東京大学)
 エプスタイン・バー(EB)ウイルスは、バーキットリンパ腫、上咽頭がん、そして胃がんの10%に関連するヒト腫瘍ウイルスです。EBウイルス胃がんでは、感染した胃上皮細胞のDNAメチル化というエピジェネティクス異常が、がんの発生に重要であることが判明しました。ウイルスの増殖をDNAメチル化によって防ごうとする細胞側の仕組みが、過剰に細胞自身にも働いてしまっている可能性があります。これらの仕組みを解明することは、がんの新しい治療法の開発につながります。>>続きはこちら
エプスタイン・バー(EB)ウイルスは、バーキットリンパ腫、上咽頭がん、そして胃がんの10%に関連するヒト腫瘍ウイルスです。EBウイルス胃がんでは、感染した胃上皮細胞のDNAメチル化というエピジェネティクス異常が、がんの発生に重要であることが判明しました。ウイルスの増殖をDNAメチル化によって防ごうとする細胞側の仕組みが、過剰に細胞自身にも働いてしまっている可能性があります。これらの仕組みを解明することは、がんの新しい治療法の開発につながります。>>続きはこちら
-
「胃がんの病理組織から診断・治療に応用できる新しいターゲットを発見する」 安井 弥 (広島大学)
 私たちは、実際のがん組織片や培養がん細胞を研究対象として、そこで機能している遺伝子を網羅的に解析し、正常の組織や細胞と比較することによって、がんがどのように発生し広がっていくかの詳しい仕組みを明らかにするとともに、新しい診断や治療のターゲットを見つけ、それを日常臨床に還元する先進医療開発の基礎的研究を行なっています。ここでは、特に胃がんについての研究のアプローチと得られた成果の一部をご紹介します。>>続きはこちら
私たちは、実際のがん組織片や培養がん細胞を研究対象として、そこで機能している遺伝子を網羅的に解析し、正常の組織や細胞と比較することによって、がんがどのように発生し広がっていくかの詳しい仕組みを明らかにするとともに、新しい診断や治療のターゲットを見つけ、それを日常臨床に還元する先進医療開発の基礎的研究を行なっています。ここでは、特に胃がんについての研究のアプローチと得られた成果の一部をご紹介します。>>続きはこちら
-
「がんの病理研究からがんの免疫・がんワクチン開発へ」 佐藤 昇志 (札幌医科大学)
 がんの免疫によるコントロールを目指し、今日まで多くの研究がなされてきました。その結果、長い間待望されていたがんワクチンが抗体創薬では臨床ですでに一部実用化され、もうひとつの大きな期待、がんペプチドは実用化一歩手前といえます。病理学は、患者さんのがんの組織を直接解析するために、これらの治療法を患者さんに適応する際に、きわめて大きな役割を担ってきています。そして、今後も病理学的研究や解析がますます重要になってくると思われます。それらの一端をご紹介します。>>続きはこちら
がんの免疫によるコントロールを目指し、今日まで多くの研究がなされてきました。その結果、長い間待望されていたがんワクチンが抗体創薬では臨床ですでに一部実用化され、もうひとつの大きな期待、がんペプチドは実用化一歩手前といえます。病理学は、患者さんのがんの組織を直接解析するために、これらの治療法を患者さんに適応する際に、きわめて大きな役割を担ってきています。そして、今後も病理学的研究や解析がますます重要になってくると思われます。それらの一端をご紹介します。>>続きはこちら
-
「急増する前立腺がんに立ち向かう基礎的研究」 白井 智之 (名古屋市立大学 名誉教授・名古屋総合リハビリテーションセンター長)
 最近急速に増加している前立腺がん。「原因は何か、増えないようにするにはどうしたらいいか、より良い治療法はないか」など前立腺がんを取り巻く重要な課題について病理学的な立場から少しでも解明したい気持ちで取り組んでいます。前立腺がんの発生機構、発生予防法、治療法を明らかにする手立てとして、ヒトの前立腺癌に類似した動物モデルを確立し、そのモデルを用いて種々の研究を進めています。ここではその研究成果についてご紹介します。>>続きはこちら
最近急速に増加している前立腺がん。「原因は何か、増えないようにするにはどうしたらいいか、より良い治療法はないか」など前立腺がんを取り巻く重要な課題について病理学的な立場から少しでも解明したい気持ちで取り組んでいます。前立腺がんの発生機構、発生予防法、治療法を明らかにする手立てとして、ヒトの前立腺癌に類似した動物モデルを確立し、そのモデルを用いて種々の研究を進めています。ここではその研究成果についてご紹介します。>>続きはこちら
-
「マクロファージを活用した診断・治療法の開発をめざす」 内藤 眞 (新潟大学)
 私たちは、マクロファージを対象として、その機能と機能の調節機構を研究しています。マクロファージは体中に存在し、代謝および感染症やがんなどの病変の中で重要な役割を果たしています。その作用の仕組みを研究することによって、病気の診断や治療に役立てることができます。ここではマクロファージの分化因子とマクロファージのスカベンジャー受容体について研究成果の一部をご紹介します。>>続きはこちら
私たちは、マクロファージを対象として、その機能と機能の調節機構を研究しています。マクロファージは体中に存在し、代謝および感染症やがんなどの病変の中で重要な役割を果たしています。その作用の仕組みを研究することによって、病気の診断や治療に役立てることができます。ここではマクロファージの分化因子とマクロファージのスカベンジャー受容体について研究成果の一部をご紹介します。>>続きはこちら
-
「光で拓く生体組織イメージング」 高松 哲郎 (京都府立医科大学)
 現在医療の現場においてCT、MRIなどのイメージング機器の果たす役割は大変大きいですが、これらのイメージング技術は原理的に低い時間・空間分解能や大掛かりな設備が必要などの問題点があります。一方、光を用いたイメージングは、分子を直接観察できる高い空間分解能とミリ秒のスピードで画像の取得が可能な高い時間分解能を持つとともに、大掛かりな設備は不要なため、病態の解析を簡便に行うことができます。>>続きはこちら
現在医療の現場においてCT、MRIなどのイメージング機器の果たす役割は大変大きいですが、これらのイメージング技術は原理的に低い時間・空間分解能や大掛かりな設備が必要などの問題点があります。一方、光を用いたイメージングは、分子を直接観察できる高い空間分解能とミリ秒のスピードで画像の取得が可能な高い時間分解能を持つとともに、大掛かりな設備は不要なため、病態の解析を簡便に行うことができます。>>続きはこちら
-
「がんの微小環境と浸潤・転移」 落合 淳志 (国立がん研究センター東病院臨床開発センター)
 「がん」とは、様々な臓器において遺伝子異常の蓄積したがん細胞が異常に増殖し、周りの組織を破壊、離れた臓器に転移・進展する悪性の腫瘍ですが、病理組織学的には、「がん」はがん細胞と炎症細胞、血管・リンパ管、線維芽細胞、細胞外基質などの間質組織より作られています。「がん」の進展は、がん細胞とその周囲組織から作られる微小環境が重要な役割を果たしていることが明らかになってきています。私たちは、がん組織を構築する間質線維芽細胞に注目し、がん間質線維芽細胞の由来や生物学的機能そしてがん細胞への影響を明らかにすることで、がん浸潤・転移機構を理解し、新しい診断法や治療法を検討してきました。 >>続きはこちら
「がん」とは、様々な臓器において遺伝子異常の蓄積したがん細胞が異常に増殖し、周りの組織を破壊、離れた臓器に転移・進展する悪性の腫瘍ですが、病理組織学的には、「がん」はがん細胞と炎症細胞、血管・リンパ管、線維芽細胞、細胞外基質などの間質組織より作られています。「がん」の進展は、がん細胞とその周囲組織から作られる微小環境が重要な役割を果たしていることが明らかになってきています。私たちは、がん組織を構築する間質線維芽細胞に注目し、がん間質線維芽細胞の由来や生物学的機能そしてがん細胞への影響を明らかにすることで、がん浸潤・転移機構を理解し、新しい診断法や治療法を検討してきました。 >>続きはこちら
-
「腎不全への進行阻止を目指した研究戦略:基礎研究からの提言」 追手 巍 (新潟医療福祉大学)
 人工透析や腎移植しか治療法が無いと言われた慢性腎不全の患者数は年々増加し、日本全体で30万人を超えています。また、この予備群である慢性腎臓病の患者数は1,300万人を超え、新しい国民病としてとらえられています。ここでは私どもの腎不全への進行阻止を目指した基礎研究とその成果を紹介します。>>続きはこちら
人工透析や腎移植しか治療法が無いと言われた慢性腎不全の患者数は年々増加し、日本全体で30万人を超えています。また、この予備群である慢性腎臓病の患者数は1,300万人を超え、新しい国民病としてとらえられています。ここでは私どもの腎不全への進行阻止を目指した基礎研究とその成果を紹介します。>>続きはこちら
-
「肝発癌モデルを通して生体内に癌が発生するメカニズムを解明する」 小川 勝洋 (旭川医科大学 名誉教授)
 私たちは動物の肝発癌モデルを通して生体内に癌が発生するメカニズムを研究しています。肝癌ができるときには、最初にまれな頻度で正常肝細胞が前癌肝細胞に変化します。このような細胞は発癌のプロセスの最初の細胞という意味でイニシエ-テット細胞と呼ばれます。前癌肝細胞は正常では肝組織内ではじっとしていますが、肝臓が慢性的に障害を受けると選択的に増殖して前癌病変を形成します。前癌肝細胞が増殖を繰り返えすと、またまれな頻度で一歩癌細胞に近づいた細胞に変わり、そのようなプロセスを重ねることによって多段階的に肝癌細胞が誕生します。>>続きはこちら
私たちは動物の肝発癌モデルを通して生体内に癌が発生するメカニズムを研究しています。肝癌ができるときには、最初にまれな頻度で正常肝細胞が前癌肝細胞に変化します。このような細胞は発癌のプロセスの最初の細胞という意味でイニシエ-テット細胞と呼ばれます。前癌肝細胞は正常では肝組織内ではじっとしていますが、肝臓が慢性的に障害を受けると選択的に増殖して前癌病変を形成します。前癌肝細胞が増殖を繰り返えすと、またまれな頻度で一歩癌細胞に近づいた細胞に変わり、そのようなプロセスを重ねることによって多段階的に肝癌細胞が誕生します。>>続きはこちら
-
「大腸がんの発生と予防を考える ー動物モデルを基礎としてー」 森 秀樹 (岐阜大学 学長)
 がんの発生と予防を研究するのに動物モデルは有用です。私の研究グループは大腸がんの発生と予防を研究する幾つかのモデルを提唱し、大腸がんの発生の早い段階の変化にどの様なものがあり、それらは遺伝子のレベルで如何なるものか、大腸がんの発生に内在・環境要因がどの様に関わるか、大腸がんの発生予防にはどの様な物質が有効で、それらはどの様に働くか、について検討してきました。ヒト大腸がんの発生と予防を理解する上で参考になれば幸いです。>>続きはこちら
がんの発生と予防を研究するのに動物モデルは有用です。私の研究グループは大腸がんの発生と予防を研究する幾つかのモデルを提唱し、大腸がんの発生の早い段階の変化にどの様なものがあり、それらは遺伝子のレベルで如何なるものか、大腸がんの発生に内在・環境要因がどの様に関わるか、大腸がんの発生予防にはどの様な物質が有効で、それらはどの様に働くか、について検討してきました。ヒト大腸がんの発生と予防を理解する上で参考になれば幸いです。>>続きはこちら
-
「自然免疫から、胆管疾患の成り立ちを考える」 中沼 安二 (金沢大学)
 胆管は、腸管と直接連続しており、そのため胆管には自然免疫を含めた感染防御機構が発達しています。胆管系疾患の成り立ちに、自然免疫が関連している疾患があります。特に、胆管上皮ではトル様受容体(TLR:Toll-like receptor)の発現があり、腸内の病原体成分がこれら受容体を反応し、胆管上皮そのものが免疫病理現象に関連し、胆管系疾患の発生と進展に関連します。これらの自然免疫の病理現象を明らかにし、疾患を治療することが可能になると期待されます。>>続きはこちら
胆管は、腸管と直接連続しており、そのため胆管には自然免疫を含めた感染防御機構が発達しています。胆管系疾患の成り立ちに、自然免疫が関連している疾患があります。特に、胆管上皮ではトル様受容体(TLR:Toll-like receptor)の発現があり、腸内の病原体成分がこれら受容体を反応し、胆管上皮そのものが免疫病理現象に関連し、胆管系疾患の発生と進展に関連します。これらの自然免疫の病理現象を明らかにし、疾患を治療することが可能になると期待されます。>>続きはこちら
-
「サイトメガロウイルスの胎内感染によって如何に脳障害が生ずるか」 筒井 祥博 (浜松医科大学 名誉教授)
 サイトメガロウイルス (CMV)は胎生期に胚や胎児に感染して脳障害を起こします。初期胚および神経発生 のはじまりの幹細胞が時間的および空間的にダイナミックに変化して形態形成、脳形成が行われています。 私たちは、神経親和性のある CMV がこの過程で如何に細胞特異的な感染感受性を示し、個体の発生、脳形成 および神経系細胞の分化の異常がもたらされるか、その病態についてマウスを用いた実験モデルで研究してきました。ヒトの症例との類似性を考慮し、解析可能なモデルとして紹介します。>>続きはこちら
サイトメガロウイルス (CMV)は胎生期に胚や胎児に感染して脳障害を起こします。初期胚および神経発生 のはじまりの幹細胞が時間的および空間的にダイナミックに変化して形態形成、脳形成が行われています。 私たちは、神経親和性のある CMV がこの過程で如何に細胞特異的な感染感受性を示し、個体の発生、脳形成 および神経系細胞の分化の異常がもたらされるか、その病態についてマウスを用いた実験モデルで研究してきました。ヒトの症例との類似性を考慮し、解析可能なモデルとして紹介します。>>続きはこちら
-
「動脈硬化症の新しい診断、治療、予防法の開発に向けた病理学からのアプローチ」居石 克夫 (国立病院機構福岡東医療センター 研究教育部・九州大学 名誉教授)
 動脈硬化は年齢とともに進行し、脂質異常症、高血圧、糖尿病、肥満等の種々の生活習慣病や喫煙等の生活習慣により促進されます。動脈硬化を基盤に発症する血管病は、死亡の原因となったり著しい生活の質的低下をもたらします。動脈硬化は「何故」、「どのようにして」、「どこに起こるのか」について進めてきた私達の研究成果の一部を紹介し、この分野における病理学的研究を基礎に展開されている臨床での具体的な応用例について述べます。>>続きはこちら
動脈硬化は年齢とともに進行し、脂質異常症、高血圧、糖尿病、肥満等の種々の生活習慣病や喫煙等の生活習慣により促進されます。動脈硬化を基盤に発症する血管病は、死亡の原因となったり著しい生活の質的低下をもたらします。動脈硬化は「何故」、「どのようにして」、「どこに起こるのか」について進めてきた私達の研究成果の一部を紹介し、この分野における病理学的研究を基礎に展開されている臨床での具体的な応用例について述べます。>>続きはこちら
-
「細胞外マトリックス分解酵素と病気」 岡田 保典 (慶応義塾大学)
 私達は、細胞間に存在する細胞外マトリックスやそれに結合した増殖因子・サイトカイン・ケモカインなどの生理活性物質を分解(代謝)するメタロプロテアーゼを標的として、ヒト悪性腫瘍におけるがん細胞の浸潤・転移、関節疾患での関節組織破壊、呼吸・循環器疾患などでの組織破壊におけるメカニズムについて研究しています。これらの疾患におけるメタロプロテアーゼの作用解析は、医学・医療の発展にも関わらずなお難治性疾患として残されている種々の疾患に対して、新規の診断法や治療法開発につながると期待しています。>>続きはこちら
私達は、細胞間に存在する細胞外マトリックスやそれに結合した増殖因子・サイトカイン・ケモカインなどの生理活性物質を分解(代謝)するメタロプロテアーゼを標的として、ヒト悪性腫瘍におけるがん細胞の浸潤・転移、関節疾患での関節組織破壊、呼吸・循環器疾患などでの組織破壊におけるメカニズムについて研究しています。これらの疾患におけるメタロプロテアーゼの作用解析は、医学・医療の発展にも関わらずなお難治性疾患として残されている種々の疾患に対して、新規の診断法や治療法開発につながると期待しています。>>続きはこちら
-
「ピロリ菌を除菌して胃がんを予防する」 立松 正衞 (元愛知県がんセンター研究所副所長)
 私たちは、胃がんの発生、進展ならびに発がん過程の修飾要因を動物実験とヒト臨床病理の両面から検討し、今後の胃がんの診断、治療ならびに予防への基礎的な情報を提供することを目的として研究を進めています。ここでは、胃がん細胞の分化異常とHelicobacter pylori (ピロリ菌)感染の胃がんの進展への影響について、研究成果の一部を紹介します。>>続きはこちら
私たちは、胃がんの発生、進展ならびに発がん過程の修飾要因を動物実験とヒト臨床病理の両面から検討し、今後の胃がんの診断、治療ならびに予防への基礎的な情報を提供することを目的として研究を進めています。ここでは、胃がん細胞の分化異常とHelicobacter pylori (ピロリ菌)感染の胃がんの進展への影響について、研究成果の一部を紹介します。>>続きはこちら
-
「炎症が持続する局所から悪性リンパ腫が発生する」 青笹 克之 (大阪大学)
 感染症からの生体の防御やがんなどの悪性腫瘍の発生を抑制する機能を担うリンパ球が無制限に増殖して腫瘤を形成し、治療しないと死に至る疾患を悪性リンパ腫と呼びます。悪性リンパ腫の中には炎症が持続している局所に腫瘍が発生する例があることに注目してきた私はその代表的な例として世界に先駆けて膿胸関連リンパ腫(pyothorax-associated lymphoma: PAL)を報告しました。PALは現在世界的によく知られています。このような研究を通じて、腫瘍の予防につながるヒントが得られるものと考えています。>>続きはこちら
感染症からの生体の防御やがんなどの悪性腫瘍の発生を抑制する機能を担うリンパ球が無制限に増殖して腫瘤を形成し、治療しないと死に至る疾患を悪性リンパ腫と呼びます。悪性リンパ腫の中には炎症が持続している局所に腫瘍が発生する例があることに注目してきた私はその代表的な例として世界に先駆けて膿胸関連リンパ腫(pyothorax-associated lymphoma: PAL)を報告しました。PALは現在世界的によく知られています。このような研究を通じて、腫瘍の予防につながるヒントが得られるものと考えています。>>続きはこちら
-
「消化管粘膜における生体防御の仕組みとその破綻による粘膜障害 ― 粘膜は生体防御の司令塔」名倉 宏 (東北大学 名誉教授)
 粘膜組織は生体と体外環境を境界し、生体に必要な物質の選択的な取り込みと体外からの様々な抗原物質の侵襲に対抗するための防御機能を備えた機能的構造的単位を構成しています。さらに粘膜系は全身の炎症免疫反応をコントロールしています。こうした粘膜での生体防御反応は神経内分泌系と密接な連関を有していることが知られています。この粘膜系の生体防御反応が破綻することにより、体外から抗原物質が生体内に侵入して炎症反応が暴走した場合、粘膜に炎症が起こり、びらんや潰瘍が形成されます。>>続きはこちら
粘膜組織は生体と体外環境を境界し、生体に必要な物質の選択的な取り込みと体外からの様々な抗原物質の侵襲に対抗するための防御機能を備えた機能的構造的単位を構成しています。さらに粘膜系は全身の炎症免疫反応をコントロールしています。こうした粘膜での生体防御反応は神経内分泌系と密接な連関を有していることが知られています。この粘膜系の生体防御反応が破綻することにより、体外から抗原物質が生体内に侵入して炎症反応が暴走した場合、粘膜に炎症が起こり、びらんや潰瘍が形成されます。>>続きはこちら
-
「がん遺伝子RETの発見によるがんの診断・治療への貢献」 髙橋 雅英 (名古屋大学)
 私たちが研究を始めた1980年頃はヒトのがんがどのようなメカニズムで発症するのか全くわかっていませんでした。80年代に入り、ヒトのがん細胞で変異が起き、がん発生の引き金になっている遺伝子異常を同定する方法が開発されました。その結果、さまざまながん細胞で変異が存在するがん遺伝子、がん抑制遺伝子とよばれる遺伝子の発見につながりました。私自身、1985年にRETと名づけたがん遺伝子を発見し、その変異が甲状腺がんや多発性内分泌腫瘍症2型とよばれる遺伝性がん、さらに最近では肺がんに存在することが明らかになり、これらのがんの診断や治療法の開発に応用されています。>>続きはこちら
私たちが研究を始めた1980年頃はヒトのがんがどのようなメカニズムで発症するのか全くわかっていませんでした。80年代に入り、ヒトのがん細胞で変異が起き、がん発生の引き金になっている遺伝子異常を同定する方法が開発されました。その結果、さまざまながん細胞で変異が存在するがん遺伝子、がん抑制遺伝子とよばれる遺伝子の発見につながりました。私自身、1985年にRETと名づけたがん遺伝子を発見し、その変異が甲状腺がんや多発性内分泌腫瘍症2型とよばれる遺伝性がん、さらに最近では肺がんに存在することが明らかになり、これらのがんの診断や治療法の開発に応用されています。>>続きはこちら
NEW
NEW
