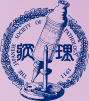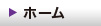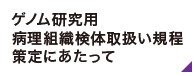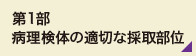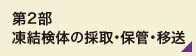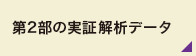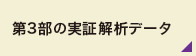第1部 研究用病理組織検体の適切な採取部位
はじめに
病理医は手術検体に対して癌の悪性度や病変の拡がり、術前治療の効果判定などを診断する。そのために手術検体をホルマリン固定した後に肉眼診断に基づいて病変部を中心とした必要部分を切り出す。この必要部分は癌取扱い規約等のルールに基づいて決定されている。
一方、ゲノム研究用の組織検体は生体内での状態に限りなく近い状態での凍結保存が理想である。そのためには、手術検体がホルマリンで固定される前の新鮮な状態で病変部を正しく見分け、病変のviableな細胞集団を可能な限り迅速に採取することが肝要である。
しかし、研究用の病理組織検体採取のために病理診断に必要な部分を誤って採取してしまうなど病理診断を阻害することがあってはならない (図1)。
したがって、研究用の組織試料はあくまで手術検体の病理診断に必要な部分を除いた部分、いわゆる残余材料から採取されるべきものである。
第1部は新鮮手術検体の残余材料から、viableな病変組織をホルマリン固定前に標準的な方法で採取できるよう、推奨する組織検体採取部位・方法をまとめて提示することを目的とする。
凡例
- (E)
- (A)よりもさらに高い品質等が期待できる場合があるが、作業量が過大である等のため、必須とは言いがたい事項
- (A)
- 推奨される事項
- (B)
- (A)が実施不可能である場合に次に推奨される事項
- (N)
- 回避すべき事項
内容について
- ベストプラクティスの形で記載するが、必ずしも実施しなければならないという訳ではない (凡例参照)。
- 腫瘍は多様であるため完全に定式化することは困難であるが、共通する内容も多いため、総論と臓器別の各論で構成する。総論では採取部位のみならず、より良い採取を行うために必要な事項について述べる。各論では臓器特異的内容について示す。主要五大癌 (肺癌・胃癌・大腸癌・乳癌・子宮癌)に関する記述が中心となるが、脳腫瘍や小児がんといった希少がんもこの規約に準拠して採取を行うことが望ましい。
- 切り出しの解説書ではない。ゆえに各臓器に対する切り出し方法についての詳細は該当する癌取扱い規約等を参考にすること。
【総論】
-
採取の原則
- 本規程で対象とする研究用組織検体はホルマリン固定前の新鮮組織検体である。採取した検体から抽出され解析となる対象はDNA・RNA・タンパク質であり、いかなる解析にも使用できる質の高い検体を採取するためには新鮮検体のなかから適正な部位を選択し、適正な手順で採取することが求められる (A)。
- 原則として、研究用組織検体採取の際にも、その基盤としての正確な良悪性の判定や組織型診断、あるいは病期の決定が重要であることは言うまでもなく、研究用組織検体採取のために病理診断に影響が出るような事態は厳に慎むべきである (N)。
- 多くの病理診断ではホルマリン固定後に手術標本の切り出しを行い、適正に作製されたHE標本の検鏡により腫瘍の範囲等を決定する。この切り出しは主に癌取扱い規約等に準拠した形で行われるが、病理診断を阻害しない適正な研究用組織検体採取を行うために各癌種における取扱い規約等を理解しておく必要がある (A)。
-
採取のために知っておくべきこと
- 採取目的:どのような目的で検体が病理部門に提出されるのかを理解しておく(A)。本規程の対象となる検体は原則治療を目的とした手術検体で通常その残余材料から検体採取を行う (A)。しかし、化学療法等の施行前や肺癌診療で遺伝子解析のために行われるRe-biopsyの際の検体は量的に少ないことが多いものの研究においても重要な検体であるため、事前に病理診断や遺伝子解析に必要な組織量を把握しておき、提出された組織検体に残余材料が発生する可能性があれば研究用組織検体として採取することも考えておく必要がある (E)。そのため、解析手法とその検体必要量について理解しておくことも望ましい (E)。
- 病変の情報収集:術前画像診断や検体検査結果等の臨床データ、術前カンファレンス等への参加により病変の場所や大きさ、拡がりなどを確認しておく (E)。感染症の有無についても確認する (A)。
- 検体提出時期と提出される検体の状態:臨床医 (外科医等)の標本整理前でかつホルマリン固定前に採取を行うためにこの時間内のどの段階で標本にどういう形で関わることになるかを理解しておく (A)。提出時期としては術中迅速、摘出直後、または手術終了後があげられる。検体の状態としては部分切除標本、全摘標本、臓器合併切除標本などである (A)。これら情報を把握することにより、採取の事前準備に役立てる (A)。
-
採取のルールを各施設で決定しておく
- 採取担当者:病理医、臨床医、臨床検査技師、バイオバンク実務担当者等 (第2部【採取者】 4.・5. 参照)。
- 採取対象:網羅的に行う (E)か特定臓器・疾患、希少癌のみ行う(A)か。境界病変、良性病変も対象とする (E)か。治療後であっても明らかに腫瘍が残存する場合には採取する (図4) (E)、など。
- 採取場所:手術室 (A)、手術標本整理室 (A)、病理切り出し室 (A)など。コンタミネーションや感染が起こりにくいよう空調や作業スペース・動線に配慮された場所が望ましい。
- 採取準備:研究用検体採取の予定日時が決まったらスタッフへの周知を行う(A)。常時対応できる体制を整えておくことも望ましい (E)。採取に必要な物品、例えば保存容器や切り出し用メス(複数必要)、液体窒素等を準備する(A)。
- 標本受け取り時の注意:標本受け取りの際に臨床上の問題点や目的を明確にしておく(A)。標本の左右、表裏等のオリエンテーション、切除断端や合併切除臓器等を確認する (A)。割を入れる方向なども可能であれば確認する (A)。できるだけ速やかな作業を心がける (A)。
-
採取部位選択-腫瘍の同定
以下の手順で行う。- 提出された手術検体に対して頭側、尾側あるいは口側、肛門側などのオリエンテーションをつける (図8、図11)。事前に決められたマーキング等を利用してもよい。
- 事前に収集した画像の情報等と照らし合わせながら腫瘍の存在場所を確認する。必要に応じて腫瘍に割をいれる。
- 腫瘍の範囲を正常と異なる形状、色調、硬度から決定する。そのためには腫瘍が存在する臓器の正常な肉眼像を知っておく必要がある。形状には隆起、陥凹、潰瘍、結節、腫瘤などがある。色調は多くは灰白色だが、黒色、赤色、黄色などがある。色調の差はホルマリン固定後には認識しやすいが、固定前には困難なことがあるため、常日頃から固定前と固定後の色調の変化について知っておくことも大事である。胃や大腸などの管腔臓器は形状が、肺や肝臓などの実質臓器は色調や硬度が重要になる。
-
採取部位の選択-割の入れ方について
- 割を入れる方向の決定には病理診断のための切り出しがどのようになされるかをシミュレーションしながら行う必要がある。この切り出す方向を決定するのに重要な因子は最大腫瘍径と腫瘍の拡がりである。
- 最大腫瘍径は原則組織の収縮などのアーティファクトのかからないホルマリン固定前に測定することになっているが、早期病変などの同定困難な腫瘍もあるので施設内で計測のルールを決めておく。
- 腫瘍の拡がりは各臓器において決められた解剖学的部位への腫瘍浸潤の有無によって評価される。そのため、決められた解剖学的部位や他臓器への浸潤が疑われる場合にはその部分には割をいれないように注意し (N)、この評価が困難になることがないように割を入れる方向を決定しなければならない。
- 特に、実質臓器における検体採取の為の割の入れ方は重要である。画像と肉眼像・組織像と比較しやすいように、割を入れる方が望ましい (A)が、部分切除や断端近傍に腫瘍が存在し断端評価が不可欠な場合などは、画像の比較にこだわらずに病理学的評価が可能な割面を出すことを優先する (E)。臨床情報を最も知る臨床医が割を入れるのも選択肢の一つである (A)。
- 実質臓器に割を入れる場合、最大腫瘍径を測定できるようにしなくてはならない(図16) (A)。その際、肉眼的に腫瘍の範囲がわかりにくい症例があること、新鮮標本に入れた割面はホルマリン固定後に凹凸ができるためトリミングが必要になることなどから固定後に顕微鏡的観察を行った上で最大腫瘍径を決定するために最大割面から若干ずらして割をいれることもある(図8、図10、図11)。
- 実質臓器の腫瘍から研究用検体を採取する場合は病理診断のための割の対面から採取する (A)。最大腫瘍径を評価するための割面から研究用組織検体の採取をおこなってはならない(N)。臓器内での腫瘍内圧が高い腫瘍では割面から膨隆する。膨隆部は切り出しの際にトリミングするため、採取を行っても病理診断に影響は出ない (図17、図35) (A)。しかし、内部に間質成分が多い腫瘍の場合、割面から膨隆しないので検体採取の際に腫瘍径に影響を与える腫瘍のスライスが必要になることがある(図20、図21、図22、図23、図24、図25、図26)。この場合、スライス厚の記録が必要である (A)。
- 直交する方向で割をいれる場合は新たな面出しのためのトリミングは不要で、一定の厚さでの正確な切り出しが可能となるが、割面の写真に採取時の切れ込みが入ってしまうなどの問題がある。
- 膵癌や乳癌などのように肉眼的な同定が困難な場合も少なくない。このような場合、固定後の変形を憚って出来るだけ小さな切れ込みから採取を行おうとすると、却って標本に不規則な凸凹が出来てしまったり、腫瘍部が採取されなかったり、などの弊害が生じる。腫瘍の肉眼観察や良好な操作の確保のために十分な割を入れ、採取後の固定時に縫合やピンで固定したりすることによって割面を平滑に保つ様々な工夫を施す方が、診断・研究のどちらにとっても望ましいことがある。ただし、腫瘍が小さく不明瞭な場合や、血管構築あるいは他臓器との関係などの複雑な解剖学的領域に腫瘍がおよぶ場合などは固定前の切開が難しい場合は無理をしないことも必要である。
-
採取部位の決定
- 癌部と非癌部 (適切な対照部位)の双方から検体を採取する (A)。この場合、採取器具は別にする (A)。やむを得ない場合には非癌部から先に採取した後に癌部の採取を行う (B)。これは、癌部検体が非癌部検体へ混入するのを防ぐためである。
- 写真撮影による採取部位の記録があるのが望ましい (E)。写真は採取前後と固定後のトリミング前の撮影が望ましい (E)。
- 採取部位には出血(赤色ないし黒色)・壊死巣 (黄色無構造) (図17、図18)を避け、viableな腫瘍組織(瑞々しい、割面から膨隆する)を選択しなければならない (図18)。Viableな腫瘍組織を選択する際には更に腫瘍の特性を最も表す部分はどこかを考えながら行わなければならない (E)。均一であれば浸潤部・非浸潤部、腫瘍先進部(境界部)・腫瘍内部などであり、不均一性が認められる場合は量的に多い部分か割面から著明に膨隆するなど悪性度が高いと考えられる組織から採取する (A)。できれば、癌部の複数箇所から組織を採取することが望ましい (図16) (E)。肉眼的な色調や形状が異なる腫瘍成分があれば、分化度や組織構築の違いなどが示唆されるため、各々について採取する (E)。 先進部は正常細胞のコンタミネーション、腫瘍内部については出血・壊死、変性部分を採取する可能性があるため注意が必要である (N) (図20)。
- 変性が加わっているところは細胞の状態が悪い、あるいは、細胞数が少ない可能性があるため、避けなければならない (N)。 胃癌、大腸癌などの管腔臓器に発生する腫瘍は中心部で潰瘍を形成することが多いため腫瘍辺縁を採取する (図2、図5、図7) (A)。逆に隆起性病変など表面でびらんをつくっている場合もあるため、注意を要する (N)。
-
性状による注意事項
- 潰瘍:中心部の壊死を採取しない (N)。
- 出血:腫瘍内に、赤色ないし黒色調に見える (図18)。
- 壊死:腫瘍内・潰瘍中心部などに、黄色調に見える (図17、図18)。
- 線維化:白色調、境界明瞭で硬い (図18)。採取は避けた方がよいが、他に採取可能な領域がなければ採取しておく。
- 粘液:粘液が多い場合 変性が少ないところ、粘液が少なく腫瘍細胞のみで構成されている部分を選ぶ (図14)。
- 粘液腫様間質:基本的に細胞成分は多くない。
- 嚢胞:嚢胞壁内に隆起性病変や壁が厚くなっているところを採取する (図30、図31、図32)。ただし、前者の場合、診断の必要量は必ず残す。
- 腫瘍細胞のみからの情報を得たい場合は、腫瘍間質が乏しく組織が軟らかい部分が好ましい。
- 転移や治療後の病変では高率に壊死や変性が加わっていることが多いため、できるだけ壊死部を避ける。
- 形状による注意事項
- 採取禁忌 (N)
- 肉眼診断困難例
-
非癌部からの採取
- 非癌部は癌の発生母地と考えられる部位を採取する(図2)。
- 非癌部にも病変がありうることを認識しておく。微小な腫瘍性病変や炎症など。後者には肝炎、膵炎、間質性肺炎などが挙げられる。
- 腫瘍近傍や腫瘍の末梢領域には腫瘍随伴性の炎症細胞浸潤や線維化を認めやすく、切離面の近くでは焼灼の影響による熱変性があるので可能な限り避ける。
-
組織採取後の取り扱い
-
サンプリングの量について
- 組織採取は病理診断を阻害しない限り多い方が望ましい (A)が、同一症例からの組織採取が多すぎると採取部位間違いなど管理を困難にする (N)ため、ある程度上限を決めておく。
【各論】
- 進行癌は最深部を採取しない
- 早期癌は採取しない
- 潰瘍を形成している場合は壊死の混入を避ける
- 断端に関する部分を採取しない
- 肺癌ではホルマリン注入が必要であるため、漏れを少なくするためにも割は必要最小限にする。
- 最大割面をずらして割を入れる。割面から膨隆することはあまりない。腫瘍中央部は線維化、大きい腫瘍では壊死している場合があるため、注意する。辺縁でviableと思われる部位を正常部の混入に注意しながら採取する。
- 胸膜に近い場合は割を入れる際に最も胸膜が嵌入した部位を避ける(図9)。
- 非浸潤癌を採取対象とするかどうか事前に決定しておく。
- 浸潤癌でも1cm未満と病変が小さい場合には病理医と相談の上、可能であれば病理診断を阻害しないよう採取量に注意して採取する。
- 粘液癌、嚢胞を伴う癌は採取場所に注意が必要である。その際、採取によって病変をなくしてしまわないよう注意する。
- 肝細胞癌は割面から膨隆するため、膨隆した部分からの採取が可能である (図17)。また、腫瘍内の不均一性のよく見られる腫瘍の一つであり、複数箇所からの採取が望まれる (図16)。
- 境界不明瞭な早期肝細胞癌では、新鮮標本での腫瘍の同定が困難であり、固定後には背景肝で観察される組織構築が不明瞭化した部分が癌部を示唆する所見となるが、採取しない判断をすることも大事である (図17)。
- 肝内胆管癌では肝細胞癌と異なり、割面から膨隆せず、腫瘍内部に線維化を伴うことが多いため、採取は腫瘍辺縁から行う (図18)。この際、正常組織の混入に注意する (図20)。
膵癌 (図21、図22、図23、図24、図25、図26、図27、図28、図29、図30、図31、図32)
- 腫瘍の中心部と思われる部分に主膵管に垂直に割を入れる。膵周囲の脈管、臓器との関係や断端が不明瞭にならないように注意する。
- 肉眼的に白色硬結を呈し、境界不明瞭なことが多く、同定し難い。更には線維形成を腫瘍内に認め、採取した組織内の腫瘍細胞成分は少ない。
- 組織採取のため割を入れた部分はホルマリン固定後の切り出し時には変形していることが多いため、組織採取後に割を入れた部分を速やかに縫合糸で閉鎖し、組織採取による切除標本の変形を極力防ぐことが必要である。
- 非癌部の採取について正常子宮内膜は高齢者の場合萎縮していることがあるので子宮内膜以外の別の近傍正常組織や末梢血などを採取しておくことも考慮する。
- 筋層浸潤の最深部が評価できるよう割の入れ方には注意する。
- 隆起性病変の場合、頂部で壊死・出血していることがあるので注意が必要。
- ポリープ状病変の場合、基部が外れないように注意する。
- 大小様々であり、採取量については大きなものは診断に差し支えないが、小さなものに対しては必要最小限に絞る必要がある。
- 腫瘍内の不均一性が見られることがあるため、複数箇所から採取する。
- 嚢胞性変化をきたしている場合は、隆起部や壁肥厚部を採取しておく。少量の場合、病理診断を優先し、無理に採取しない。
- 境界病変については採取対象とするかどうか決めておく。その際、後の病理診断で診断が変わりうることを認識しておく。採取部位の組織がわかるよう採取検体の一部の凍結切片あるいは捺印細胞診、あるいは固定後に対応する部位の切り出しを行っておく。
軟部腫瘍 (図39)
- 希少症例、診断困難と思われる症例は可能な限り組織検体を採取しておく。
- 腫瘍によっては腫瘍内不均一性が認められる腫瘍があり、複数箇所からの採取が求められる。