募集の最近のブログ記事
2025年2月 4日
【募集期間再延長】第7回(2025年度)ハンガリー病理解剖トレーニングコース 参加者募集
2025年3月3日
日本病理学会海外研修委員会 委員長
黒瀬 顕
日本病理学会海外研修委員会 委員長
黒瀬 顕
---下記、第7回ハンガリー病理解剖トレーニングコースについて、1月末までの募集としておりましたが、まだ若干名の空きがございますので、募集期間を3月15日まで延長いたします。奮ってのご応募をお待ちしております---
近年、日本を含む世界各国で病理解剖数が減少傾向にあり、特に若手病理医が国内で十分な解剖経験を積むことが困難な状況にあります。一方、ハンガリーでは現在も多数の病理解剖が行われています。そこで日本病理学会では、ハンガリー最大の医科大学であるSemmelweis大学と提携し、日本の病理医がハンガリーで短期集中的に病理解剖の経験を積むことができるトレーニングコースを創設しました。
このコースでは、指導教官の下、参加者自らが病理解剖を行い、臓器観察後臨床病理相関をつけ、報告書にまとめるまでの作業を行います。短期間にこれら業務を繰り返すことによって、所見の取り方、病態の理解、報告書作成能力の修得、向上が期待されます。また国際交流としても貴重な経験を得ることができます。
本コースは2014年に試行されたのち、2015年から2019年まで毎年夏に1回、計5回実施され、のべ22名が参加し充実した成果をあげることができました。2020年以降はコロナ禍のため中止しておりましたが、2024年度に第6回として再開され、5名が参加しました。第7回となる2025年度は以下の要領でコース参加者を募集します。奮ってご応募ください。
募集要項
1)実施期間
① 事前自習コース: ~2025年6月27日(金)
② 実地実習コース: 2025年8月10日(日)午後6時~8月16日(土)夕方
(①と②の両方を受講いただきます)
2)場所
Semmelweis大学第二病理学教室(ハンガリー ブダペスト)
3)コース責任者
Kiss András (Semmelweis大学第二病理学教室 教授)
4)コース内容
① 事前自習コース: 配布資料を熟読し、病理解剖に必要な英語用語、英文解剖報告書作成要領を習得する。自験例1例を作成要領に沿って作成し、6月27日までに日本病理学会事務局へ提出する。
注) コース初日から病理解剖が行われるため英文での病理解剖レポート作成を事前学習しておく必要があります。配付資料(用語集、過去の校閲済み英文報告書例が含まれます)を参考に各自が過去に執刀した任意の病理解剖一症例につき、作成要領に沿って英文での病理解剖レポートを作成し提出して下さい。レポート提出以外の事前学習は各自に委ねます。
② 実地実習コース: Semmelweis大学第二病理学教室のスタッフの指導の下で実際に病理解剖を行い、解剖報告書(英語)を作成する。月曜午前のオリエンテーション、病理解剖講義と説明(剖検手順、観察、レポート作成要領等)に引き続き、月曜午後から金曜午後までに合計10体の病理解剖を参加者自ら実施する。土曜日に修了証書が授与される。
5)応募資格
日本病理学会会員で、病理解剖を集中して学びたい医師及び歯科医師。
病理専門医あるいは死体解剖資格の有無は問わないが、日本での病理解剖の経験が10~15体程度あることが望ましい。
6)費用
選考の結果参加が確定した者は、コース受講費用として一人50万円を5月19日までに日本病理学会へ支払うこと。
注1)なおこの金額には、現地への渡航費及び滞在費(30万円程度の見込み)は含まれていないことにご注意ください。コース受講費用、渡航費、滞在費は自己負担(可能であれば所属機関の負担)となります。
注2)キャンセルする場合はコース開始日から起算し10週間前(2025年6月1日)までに病理学会事務局へ連絡すること。
注3)2025年7月29日を過ぎてコースへの参加をキャンセルする場合は、理由の如何によらず、コース受講費用の全額を払う必要がある。
7)募集人数
4名
8)応募期限
2025年3月15日(土) 必着
9)応募方法
申込用紙(別紙)を病理学会ホームページよりダウンロードし、必要事項を記入の上、日本病理学会事務局(jsp.office@pathology.or.jp)までメールすること。
10)選考
日本病理学会海外研修委員会で選考する。なお、応募者多数の場合は、病理専門医試験受験前の方を優先することがある。
選考結果は2025年3月末までに申込者本人へ通知する。
11)参加者の提出書類
選考の結果、コースに参加することが確定した者は、別途連絡する期日までに下記書類をSemmelweis大学第二病理学教室へ提出すること。
(a)パスポート(顔写真のあるページ)の写し
(b)大学及び大学院(博士号を取得している場合)の卒業証明書(英文)
(c)医師(歯科医師)免許証(和文)の写し
(d)参加者が医師免許を有することを証明する文書(英文)(書式自由)
(e)参加者の予防接種歴の有無と抗体価の証明書(英文)(書式自由)
(d)及び(e)には所属する部署の責任者(教授や部長等)のサインが必要である。なお、(c)の代わりに厚生労働省の 発行する英文の医師または歯科医師の免許証を提出する場合は、(d)は不要である。(e)については参加者の所属 する医療機関で診療にあたり必要とされている予防接種の項目(麻疹やHBV等)について記載すること。
12)申込後のキャンセルについて
申込後、コースへの参加が困難になった場合は日本病理学会事務局へ速やかに連絡すること。但し選考を経て受講が正式に決定した後に参加を辞退する場合、他の参加予定者にも影響が出る場合があるので、選考終了後の参加辞退はできる限り避けること。2025年7月29日を過ぎてコースへの参加をキャンセルする場合は、理由の如何によらず、コース受講費用の全額を払う必要がある。
13)その他
コース修了者にはSemmelweis大学より受講証が交付される。受講証の写しを病理専門医試験受験申請時に提出することで、病理専門医試験受験に必要な病理解剖経験数のうち4体に充てることができる。
なお過去のハンガリー病理解剖トレーニングコース体験記は、病理学会ホームページの「会員専用情報」に掲載されている。
問い合わせ先
日本病理学会事務局
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町2-17 神田INビル6階
TEL 03-6206-9070
FAX 03-6206-9077
E-mail: jsp.office@pathology.or.jp
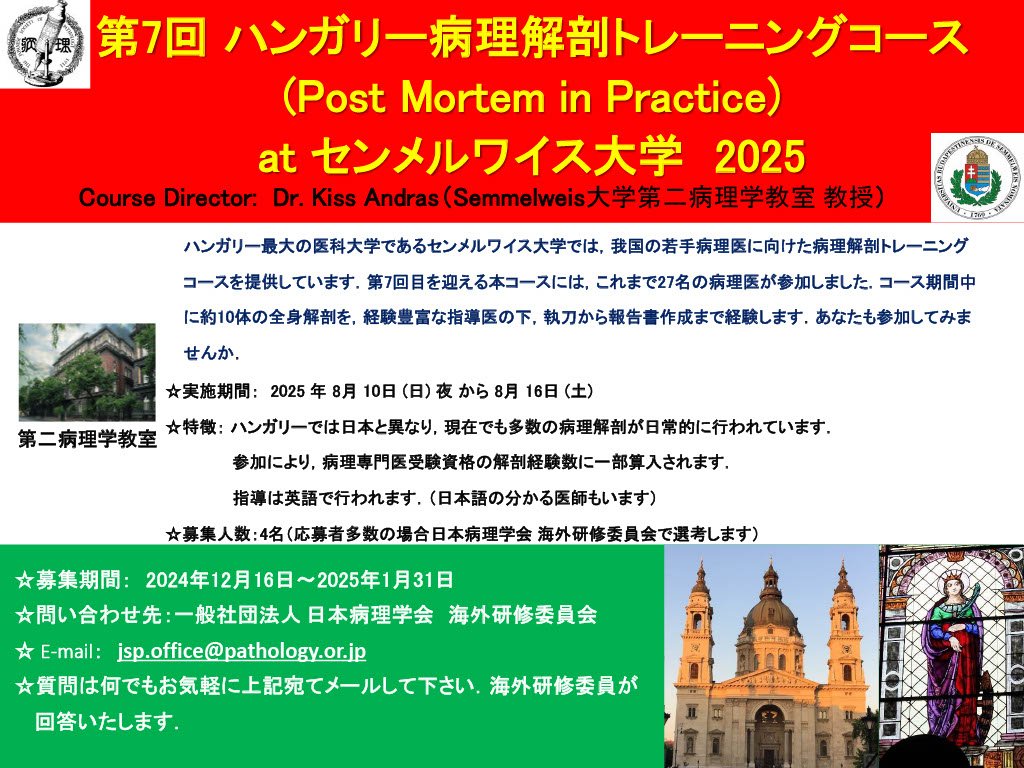
2024年12月 4日
第7回(2025年度)ハンガリー病理解剖トレーニングコース 参加者募集
2024年12月4日
日本病理学会海外研修委員会 委員長
黒瀬 顕
日本病理学会海外研修委員会 委員長
黒瀬 顕
近年、日本を含む世界各国で病理解剖数が減少傾向にあり、特に若手病理医が国内で十分な解剖経験を積むことが困難な状況にあります。一方、ハンガリーでは現在も多数の病理解剖が行われています。そこで日本病理学会では、ハンガリー最大の医科大学であるSemmelweis大学と提携し、日本の病理医がハンガリーで短期集中的に病理解剖の経験を積むことができるトレーニングコースを創設しました。
このコースでは、指導教官の下、参加者自らが病理解剖を行い、臓器観察後臨床病理相関をつけ、報告書にまとめるまでの作業を行います。短期間にこれら業務を繰り返すことによって、所見の取り方、病態の理解、報告書作成能力の修得、向上が期待されます。また国際交流としても貴重な経験を得ることができます。
本コースは2014年に試行されたのち、2015年から2019年まで毎年夏に1回、計5回実施され、のべ22名が参加し充実した成果をあげることができました。2020年以降はコロナ禍のため中止しておりましたが、2024年度に第6回として再開され、5名が参加しました。第7回となる2025年度は以下の要領でコース参加者を募集します。奮ってご応募ください。
募集要項
1)実施期間
① 事前自習コース: ~2025年6月27日(金)
② 実地実習コース: 2025年8月10日(日)午後6時~8月16日(土)正午
(①と②の両方を受講いただきます)
2)場所
Semmelweis大学第二病理学教室(ハンガリー ブダペスト)
3)コース責任者
Kiss András (Semmelweis大学第二病理学教室 教授)
4)コース内容
① 事前自習コース: 配布資料を熟読し、病理解剖に必要な英語用語、英文解剖報告書作成要領を習得する。自験例1例を作成要領に沿って作成し、6月27日までに日本病理学会事務局へ提出する。
注) コース初日から病理解剖が行われるため英文での病理解剖レポート作成を事前学習しておく必要があります。配付資料(用語集、過去の校閲済み英文報告書例が含まれます)を参考に各自が過去に執刀した任意の病理解剖一症例につき、作成要領に沿って英文での病理解剖レポートを作成し提出して下さい。レポート提出以外の事前学習は各自に委ねます。
② 実地実習コース: Semmelweis大学第二病理学教室のスタッフの指導の下で実際に病理解剖を行い、解剖報告書(英語)を作成する。月曜午前のオリエンテーション、病理解剖講義と説明(剖検手順、観察、レポート作成要領等)に引き続き、月曜午後から金曜午後までに合計10体の病理解剖を参加者自ら実施する。土曜日に修了証書が授与される。
5)応募資格
日本病理学会会員で、病理解剖を集中して学びたい医師及び歯科医師。
病理専門医あるいは死体解剖資格の有無は問わないが、日本での病理解剖の経験が10~15体程度あることが望ましい。
6)費用
選考の結果参加が確定した者は、コース受講費用として一人50万円を5月19日までに日本病理学会へ支払うこと。
注1)なおこの金額には、現地への渡航費及び滞在費(30万円程度の見込み)は含まれていないことにご注意ください。コース受講費用、渡航費、滞在費は自己負担(可能であれば所属機関の負担)となります。
注2)キャンセルする場合はコース開始日から起算し10週間前(2025年6月1日)までに病理学会事務局へ連絡すること。
注3)2025年7月29日を過ぎてコースへの参加をキャンセルする場合は、理由の如何によらず、コース受講費用の全額を払う必要がある。
7)募集人数
4名
8)応募期限
2025年1月31日(金) 必着(4人に満たない場合は延長します)
9)応募方法
申込用紙(別紙)を病理学会ホームページよりダウンロードし、必要事項を記入の上、日本病理学会事務局(jsp.office@pathology.or.jp)までメールすること。
10)選考
日本病理学会海外研修委員会で選考する。なお、応募者多数の場合は、病理専門医試験受験前の方を優先することがある。
選考結果は2025年3月末までに申込者本人へ通知する。
11)参加者の提出書類
選考の結果、コースに参加することが確定した者は、別途連絡する期日までに下記書類をSemmelweis大学第二病理学教室へ提出すること。
(a)パスポート(顔写真のあるページ)の写し
(b)大学及び大学院(博士号を取得している場合)の卒業証明書(英文)
(c)医師(歯科医師)免許証(和文)の写し
(d)参加者が医師免許を有することを証明する文書(英文)(書式自由)
(e)参加者の予防接種歴の有無と抗体価の証明書(英文)(書式自由)
(d)及び(e)には所属する部署の責任者(教授や部長等)のサインが必要である。なお、(c)の代わりに厚生労働省の 発行する英文の医師または歯科医師の免許証を提出する場合は、(d)は不要である。(e)については参加者の所属 する医療機関で診療にあたり必要とされている予防接種の項目(麻疹やHBV等)について記載すること。
12)申込後のキャンセルについて
申込後、コースへの参加が困難になった場合は日本病理学会事務局へ速やかに連絡すること。但し選考を経て受講が正式に決定した後に参加を辞退する場合、他の参加予定者にも影響が出る場合があるので、選考終了後の参加辞退はできる限り避けること。2025年7月29日を過ぎてコースへの参加をキャンセルする場合は、理由の如何によらず、コース受講費用の全額を払う必要がある。
13)その他
コース修了者にはSemmelweis大学より受講証が交付される。受講証の写しを病理専門医試験受験申請時に提出することで、病理専門医試験受験に必要な病理解剖経験数のうち4体に充てることができる。
なお過去のハンガリー病理解剖トレーニングコース体験記は、病理学会ホームページの「会員専用情報」に掲載されている。
問い合わせ先
日本病理学会事務局
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町2-17 神田INビル6階
TEL 03-6206-9070
FAX 03-6206-9077
E-mail: jsp.office@pathology.or.jp
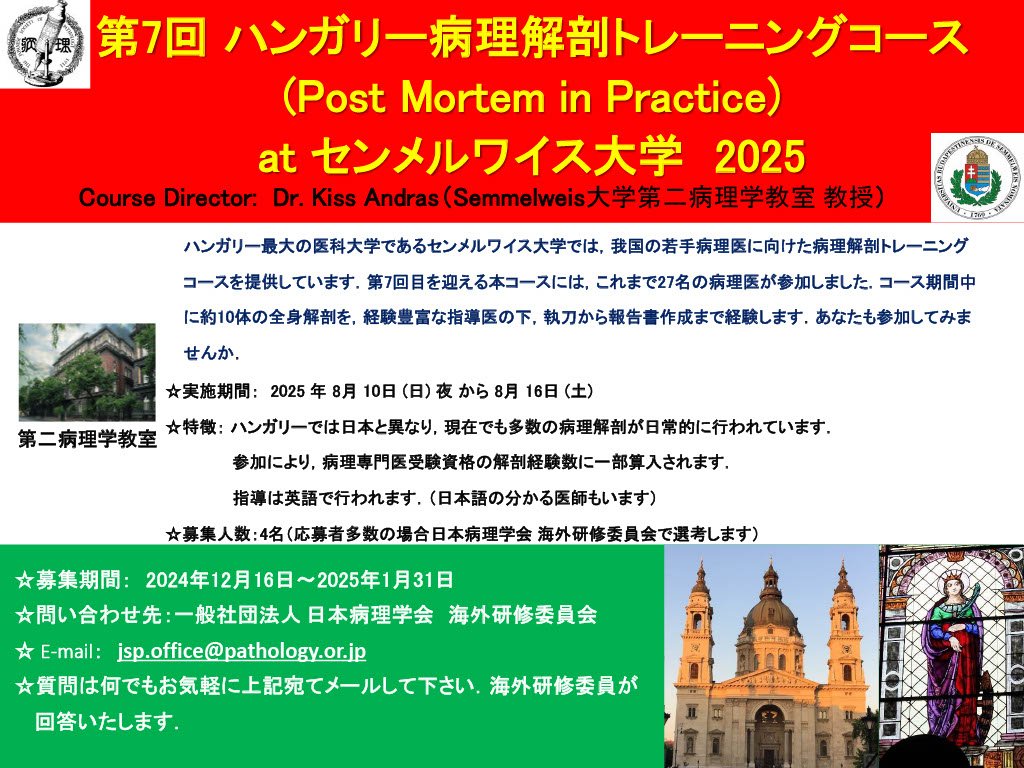
2024年6月24日
第115回(令和8年度)総会における宿題報告担当者の募集と宿題報告担当候補者の推薦について
第115回(令和8年度)総会における宿題報告担当者の募集について(公募)
標記の件、下記の要領にてご応募をお願いいたします。尚、担当者には「日本病理学賞」が授与されます。
宿題報告(日本病理学賞)とは:
日本病理学賞は、病理学領域における特定の課題について卓越した業績を挙げていると判断された会員が、その課題の業績を日本病理学会総会において報告し、もって会員の病理に関する学術、医療の振興とその普及に資することを企図して設けられた宿題報告の担当者に授与されます。宿題報告は1911年開催の第1回総会から行われ100年以上の歴史があります。
宿題報告の内容は、以下の要件を満たすものとする。
(1)国内外の評価のある業績であること。
(2)断片としての学術情報ではなく、体系として受け取れる内容であること。
(3)演者の示す問題把握のしかた、課題の解決法、学問観などが会員にとって大いに資するものであること。
尚、Pathology International へ総説を投稿すること
1.応募資格:
日本病理学会学術評議員(ただし昭和35年4月2日以降生まれの者)
2.募集人員:
3名以内
3.提出書類:
※応募書類は以下をPDF化した電子媒体(すべての書類をひとつのPDFファイルとしてつなげたもの)にて提出していただくことになりました。
(1) 宿題報告応募用紙 書式はこちらから(word形式)
所定の書式に、応募者名、演題名、選考用抄録(1,100字以内)などを記載したもの。
(2) 論文業績一覧
講演内容に直接関係のある自著論文50編以内の一覧。主要論文(10編以内)の番号に「〇」印を付し、要旨を日本語300字以内で記載すること。
(3) 主要論文10編以内の別刷
上記(1)~(3)の書類を、順番にひとつのPDFファイルにつなげてお送り下さい。
*ひとつのフォルダ内に複数のPDF化した書類を入れて提出されたものはお受け取りできません。
提出先:
日本病理学会事務局
4.提出方法
(1) 応募書類送付の前に、応募申請のE-mailをお送り下さい。E-mail: jsp.office@pathology.or.jp
申請メールと応募書類の2つがそろって応募完了となりますのでご留意下さい。
①E-mailの件名として 「令和8年度宿題報告応募申請」とし、その後ろにご自身の会員番号も記載して下さい。
②1.送信予定日時 2.氏名 3.所属(教室名まで正式名称を)4.演題名を記載して下さい。
(2) 上記 (1) の申請メール送信後、応募書類(すべての書類をひとつのPDFファイルにつなげたもの)をPDF電子媒体として下記のURLよりアップロードして下さい。
応募書類提出先: https://biz.datadeliver.net/posts/syukudai2024
①アップロードの際にコメント欄にお名前と会員番号を記入して下さい。
②ファイル受領から「業務日」3日以内に事前にお送りいただいた申請メールに受領の旨を返信いたします。受領のメールが届かない場合は、すみやかに事務局宛にお問い合わせ下さい。
③各種連絡や審査用資料の作成については、会員システム登録の情報を元に行われます。事前に登録内容の確認、修正をお願いします。
5.締め切り: 令和6年8月18日(日)必着
なお、第115回日本病理学会における宿題報告担当者は、令和6年秋の学術委員会において厳正・公明に選考し、同年11月の理事会審議にて決定後、社員総会にて公表いたします。
また、担当者には以下のご依頼をさしあげますのでご承知置き下さい。
①発表抄録の日・英両言語での作成
②「病理学の研究でわかること」(https://pathology.or.jp/ippan/info-trans.html)の原稿作成
本件につきましてご質問がありましたら、日本病理学会事務局または学術委員長までお問い合せください。
学術委員長(田中伸哉)
日本病理学会事務局:TEL 03-6206-9070 FAX 03-6206-9077 E-mail: jsp.office@pathology.or.jp
宿題報告担当者については原則、自薦としますが、学術評議員からの推薦も受けております。下記の要領で、宿題報告担当候補者の推薦をお願いいたします。学術評議員から推薦された候補者については、学術委員長名で推薦されている旨をご本人にお伝えし、応募されることをお勧めいたします。
推薦方法: 日本病理学会ホームページよりダウンロードした所定の書式に、被推薦者名、演題(発表していただきたい内容)、簡単な推薦理由、推薦者名、などを記載して下さい。そちらをPDF化した上で、E-mail添付にて下記にお送り下さい。
書式はこちらから(word形式)
提出先:
日本病理学会事務局 jsp.office@pathology.or.jp
E-mail の件名は「令和8年度宿題報告担当者推薦」として下さい。
推薦締め切り: 令和6年7月17日(水)
本件につきましてご質問がありましたら、日本病理学会事務局または学術委員長までお問い合せ下さい。
学術委員長(田中伸哉)
日本病理学会事務局:TEL 03-6206-9070 FAX 03-6206-9077 E-mail: jsp.office@pathology.or.jp
標記の件、下記の要領にてご応募をお願いいたします。尚、担当者には「日本病理学賞」が授与されます。
宿題報告(日本病理学賞)とは:
日本病理学賞は、病理学領域における特定の課題について卓越した業績を挙げていると判断された会員が、その課題の業績を日本病理学会総会において報告し、もって会員の病理に関する学術、医療の振興とその普及に資することを企図して設けられた宿題報告の担当者に授与されます。宿題報告は1911年開催の第1回総会から行われ100年以上の歴史があります。
宿題報告の内容は、以下の要件を満たすものとする。
(1)国内外の評価のある業績であること。
(2)断片としての学術情報ではなく、体系として受け取れる内容であること。
(3)演者の示す問題把握のしかた、課題の解決法、学問観などが会員にとって大いに資するものであること。
尚、Pathology International へ総説を投稿すること
1.応募資格:
日本病理学会学術評議員(ただし昭和35年4月2日以降生まれの者)
2.募集人員:
3名以内
3.提出書類:
※応募書類は以下をPDF化した電子媒体(すべての書類をひとつのPDFファイルとしてつなげたもの)にて提出していただくことになりました。
(1) 宿題報告応募用紙 書式はこちらから(word形式)
所定の書式に、応募者名、演題名、選考用抄録(1,100字以内)などを記載したもの。
(2) 論文業績一覧
講演内容に直接関係のある自著論文50編以内の一覧。主要論文(10編以内)の番号に「〇」印を付し、要旨を日本語300字以内で記載すること。
(3) 主要論文10編以内の別刷
上記(1)~(3)の書類を、順番にひとつのPDFファイルにつなげてお送り下さい。
*ひとつのフォルダ内に複数のPDF化した書類を入れて提出されたものはお受け取りできません。
提出先:
日本病理学会事務局
4.提出方法
(1) 応募書類送付の前に、応募申請のE-mailをお送り下さい。E-mail: jsp.office@pathology.or.jp
申請メールと応募書類の2つがそろって応募完了となりますのでご留意下さい。
①E-mailの件名として 「令和8年度宿題報告応募申請」とし、その後ろにご自身の会員番号も記載して下さい。
②1.送信予定日時 2.氏名 3.所属(教室名まで正式名称を)4.演題名を記載して下さい。
(2) 上記 (1) の申請メール送信後、応募書類(すべての書類をひとつのPDFファイルにつなげたもの)をPDF電子媒体として下記のURLよりアップロードして下さい。
応募書類提出先: https://biz.datadeliver.net/posts/syukudai2024
①アップロードの際にコメント欄にお名前と会員番号を記入して下さい。
②ファイル受領から「業務日」3日以内に事前にお送りいただいた申請メールに受領の旨を返信いたします。受領のメールが届かない場合は、すみやかに事務局宛にお問い合わせ下さい。
③各種連絡や審査用資料の作成については、会員システム登録の情報を元に行われます。事前に登録内容の確認、修正をお願いします。
5.締め切り: 令和6年8月18日(日)必着
なお、第115回日本病理学会における宿題報告担当者は、令和6年秋の学術委員会において厳正・公明に選考し、同年11月の理事会審議にて決定後、社員総会にて公表いたします。
また、担当者には以下のご依頼をさしあげますのでご承知置き下さい。
①発表抄録の日・英両言語での作成
②「病理学の研究でわかること」(https://pathology.or.jp/ippan/info-trans.html)の原稿作成
本件につきましてご質問がありましたら、日本病理学会事務局または学術委員長までお問い合せください。
学術委員長(田中伸哉)
日本病理学会事務局:TEL 03-6206-9070 FAX 03-6206-9077 E-mail: jsp.office@pathology.or.jp
第115回(令和8年度)日本病理学会総会における宿題報告担当候補者の推薦について
宿題報告担当者については原則、自薦としますが、学術評議員からの推薦も受けております。下記の要領で、宿題報告担当候補者の推薦をお願いいたします。学術評議員から推薦された候補者については、学術委員長名で推薦されている旨をご本人にお伝えし、応募されることをお勧めいたします。
推薦方法: 日本病理学会ホームページよりダウンロードした所定の書式に、被推薦者名、演題(発表していただきたい内容)、簡単な推薦理由、推薦者名、などを記載して下さい。そちらをPDF化した上で、E-mail添付にて下記にお送り下さい。
書式はこちらから(word形式)
提出先:
日本病理学会事務局 jsp.office@pathology.or.jp
E-mail の件名は「令和8年度宿題報告担当者推薦」として下さい。
推薦締め切り: 令和6年7月17日(水)
本件につきましてご質問がありましたら、日本病理学会事務局または学術委員長までお問い合せ下さい。
学術委員長(田中伸哉)
日本病理学会事務局:TEL 03-6206-9070 FAX 03-6206-9077 E-mail: jsp.office@pathology.or.jp
第71回(令和7年度)日本病理学会秋期特別総会における病理診断特別講演担当候補者の公募と推薦について
病理診断特別講演担当候補者の公募について
標記の件、下記の要領にてご応募をお願いいたします。尚、担当者には「病理診断学賞」が授与されます。
病理診断特別講演(病理診断学賞)とは:
病理診断学賞は、特定の疾患や臓器における病理診断に関して、本学会に永年にわたって貢献し、その専門に卓越した業績と見識をもつ本学会員が担当し、担当疾患の病理診断に関して主として解説的に講演する病理診断特別講演の担当者に授与されます。
病理診断特別講演の内容は、以下の要件を満たすものとする。
(1)国内外の評価のある業績であること。
(2)断片としての学術情報ではなく、体系として受け取れる内容であること。
(3)演者の示す疾患分類、診断、レポートなど病理診断に関わる考え方や病理診断学における学問観などが会員にとって大いに資するものであること。
尚、Pathology International へ総説を投稿すること
1.応募資格:
応募時において日本病理学会学術評議員であること
2.募集人員:
2名以内
3.提出書類:
※応募書類は以下をPDF化した電子媒体(すべての書類をひとつのPDFファイルとしてつなげたもの)にて提出していただくことになりました。
1)「病理診断特別講演」担当者応募用紙
応募者名、略歴、課題名、応募理由(1100字以内)等を記載したもの。
書式はこちらから(word形式)
※書式はWord形式です。全体が適切な形で2ページ以内に収まるよう配慮して下さい。
2)病理診断特別講演選考用関連業績一覧
応募理由に関する(1)病理診断に関する活動・功績、(2)学術講演の経験、(3)書著、(4)論文(20編以内)
上記1)、2)の書類を、順番にひとつのPDFファイルにつなげてお送り下さい。
*ひとつのフォルダ内に複数のPDF化した書類を入れて提出されたものはお受け取りできません。
提出先:
日本病理学会事務局
4.提出方法:
(1)応募書類送付の前に、応募申請のE-mailをお送り下さい。E-mail: jsp.office@pathology.or.jp
申請メールと応募書類の2つがそろって応募完了となりますのでご留意下さい。
①E-mailの件名として 「令和7年度病理診断特別講演応募申請」とし、その後ろにご自身の会員番号も記載して下さい。
②1.送信予定日時 2.氏名 3.所属(教室名まで正式名称を)4.演題名を記載して下さい。
(2)上記(1)の申請メール送信後、応募書類(すべての書類をひとつのPDFファイルにつなげたもの)をPDF電子媒体として下記のURLよりアップロードして下さい。
応募書類の提出先: https://biz.datadeliver.net/posts/kouen2024
①アップロードの際にコメント欄にお名前と会員番号を記入して下さい。
②ファイル受領から「業務日」3日以内に事前にお送りいただいた申請メールに受領の旨を返信いたします。受領のメールが届かない場合は、すみやかに事務局宛にお問い合わせ下さい。
③各種連絡や審査用資料の作成については、会員システム登録の情報を元に行われます。事前に登録内容の確認、修正をお願いします。
締め切り:
令和6年8月18日(日)必着
担当者は令和6年秋の学術委員会において厳正・公明に選考し、同年11月の理事会審議にて決定後、社員総会にて公表いたします。
担当者には発表抄録の日・英両言語での作成をお願いします。
本件につきましてご質問がありましたら、日本病理学会事務局または学術委員長までお問い合せ下さい。
学術委員長(田中伸哉)
日本病理学会事務局:TEL 03-6206-9070 FAX 03-6206-9077 E-mail: jsp.office@pathology.or.jp
病理診断特別講演担当者については原則、自薦としますが、学術評議員からの推薦も受けております。下記の要領で、候補者のご推薦をお願いいたします。学術評議員から推薦された候補者については、学術委員長名で推薦されている旨をご本人にお伝えし、応募されることをお勧めいたします。
推薦方法:
日本病理学会ホームページよりダウンロードした所定の書式に、被推薦者名、演題(発表していただきたい内容)、簡単な推薦理由、推薦者名、などを記載して下さい。そちらをPDF化した上で、E-mail添付にて下記にお送り下さい。
書式はこちらから(word形式)
提出先:
日本病理学会事務局 jsp.office@pathology.or.jp
E-mail の件名は「令和7年度病理診断特別講演担当者推薦」として下さい。
推薦締め切り:
令和6年7月17日(水)
本件につきましてご質問がありましたら、日本病理学会事務局または学術委員長までお問い合せ下さい。
学術委員長(田中伸哉)
日本病理学会事務局:TEL 03-6206-9070 FAX 03-6206-9077 E-mail: jsp.office@pathology.or.jp
標記の件、下記の要領にてご応募をお願いいたします。尚、担当者には「病理診断学賞」が授与されます。
病理診断特別講演(病理診断学賞)とは:
病理診断学賞は、特定の疾患や臓器における病理診断に関して、本学会に永年にわたって貢献し、その専門に卓越した業績と見識をもつ本学会員が担当し、担当疾患の病理診断に関して主として解説的に講演する病理診断特別講演の担当者に授与されます。
病理診断特別講演の内容は、以下の要件を満たすものとする。
(1)国内外の評価のある業績であること。
(2)断片としての学術情報ではなく、体系として受け取れる内容であること。
(3)演者の示す疾患分類、診断、レポートなど病理診断に関わる考え方や病理診断学における学問観などが会員にとって大いに資するものであること。
尚、Pathology International へ総説を投稿すること
1.応募資格:
応募時において日本病理学会学術評議員であること
2.募集人員:
2名以内
3.提出書類:
※応募書類は以下をPDF化した電子媒体(すべての書類をひとつのPDFファイルとしてつなげたもの)にて提出していただくことになりました。
1)「病理診断特別講演」担当者応募用紙
応募者名、略歴、課題名、応募理由(1100字以内)等を記載したもの。
書式はこちらから(word形式)
※書式はWord形式です。全体が適切な形で2ページ以内に収まるよう配慮して下さい。
2)病理診断特別講演選考用関連業績一覧
応募理由に関する(1)病理診断に関する活動・功績、(2)学術講演の経験、(3)書著、(4)論文(20編以内)
上記1)、2)の書類を、順番にひとつのPDFファイルにつなげてお送り下さい。
*ひとつのフォルダ内に複数のPDF化した書類を入れて提出されたものはお受け取りできません。
提出先:
日本病理学会事務局
4.提出方法:
(1)応募書類送付の前に、応募申請のE-mailをお送り下さい。E-mail: jsp.office@pathology.or.jp
申請メールと応募書類の2つがそろって応募完了となりますのでご留意下さい。
①E-mailの件名として 「令和7年度病理診断特別講演応募申請」とし、その後ろにご自身の会員番号も記載して下さい。
②1.送信予定日時 2.氏名 3.所属(教室名まで正式名称を)4.演題名を記載して下さい。
(2)上記(1)の申請メール送信後、応募書類(すべての書類をひとつのPDFファイルにつなげたもの)をPDF電子媒体として下記のURLよりアップロードして下さい。
応募書類の提出先: https://biz.datadeliver.net/posts/kouen2024
①アップロードの際にコメント欄にお名前と会員番号を記入して下さい。
②ファイル受領から「業務日」3日以内に事前にお送りいただいた申請メールに受領の旨を返信いたします。受領のメールが届かない場合は、すみやかに事務局宛にお問い合わせ下さい。
③各種連絡や審査用資料の作成については、会員システム登録の情報を元に行われます。事前に登録内容の確認、修正をお願いします。
締め切り:
令和6年8月18日(日)必着
担当者は令和6年秋の学術委員会において厳正・公明に選考し、同年11月の理事会審議にて決定後、社員総会にて公表いたします。
担当者には発表抄録の日・英両言語での作成をお願いします。
本件につきましてご質問がありましたら、日本病理学会事務局または学術委員長までお問い合せ下さい。
学術委員長(田中伸哉)
日本病理学会事務局:TEL 03-6206-9070 FAX 03-6206-9077 E-mail: jsp.office@pathology.or.jp
第71回(令和7年度)日本病理学会秋期特別総会における病理診断特別講演担当候補者の推薦について
病理診断特別講演担当者については原則、自薦としますが、学術評議員からの推薦も受けております。下記の要領で、候補者のご推薦をお願いいたします。学術評議員から推薦された候補者については、学術委員長名で推薦されている旨をご本人にお伝えし、応募されることをお勧めいたします。
推薦方法:
日本病理学会ホームページよりダウンロードした所定の書式に、被推薦者名、演題(発表していただきたい内容)、簡単な推薦理由、推薦者名、などを記載して下さい。そちらをPDF化した上で、E-mail添付にて下記にお送り下さい。
書式はこちらから(word形式)
提出先:
日本病理学会事務局 jsp.office@pathology.or.jp
E-mail の件名は「令和7年度病理診断特別講演担当者推薦」として下さい。
推薦締め切り:
令和6年7月17日(水)
本件につきましてご質問がありましたら、日本病理学会事務局または学術委員長までお問い合せ下さい。
学術委員長(田中伸哉)
日本病理学会事務局:TEL 03-6206-9070 FAX 03-6206-9077 E-mail: jsp.office@pathology.or.jp