2016年7月アーカイブ
2016年7月19日
第63回(平成29年度)日本病理学会秋期特別総会における病理診断特別講演(旧:診断シリーズ)担当候補者の推薦について
この度、「診断シリーズ」を新たに「病理診断特別講演」と位置づけ、その担当者には「病理診断学賞」を授与することといたしました(平成28年3月理事会決定)。
つきましては、標記担当者の推薦を受けつけいたします。自薦、他薦はといません。下記の要領にてご推薦をお願いいたします。
病理診断特別講演とは:
「病理診断特別講演」は、特定の疾患や臓器における病理診断に関して、本学会に永年にわたって貢献し、その専門に卓越した経験と見識をもつ本学会員が担当し、担当疾患の病理診断に関して主として解説的に講演する。「病理診断特別講演」担当者には、「病理診断学賞」が授与される。
推薦者:
推薦者は、学術評議員であること。自薦も可とします。他薦では被推薦者の内諾を要します。
推薦書式:
1)下記よりダウンロードした所定の推薦書式に推薦者名、候補者名、略歴、活動・功績、課題名、推薦/申請理由(1000字以内)等を記載したもの。
※書式はWord形式です。全体が適切な形で2ページ以内に収まるよう配慮して下さい。
自薦はこちら 他薦はこちら
2)推薦理由に関する論文・著書業績(20編以内)のリスト
提出先:
一般社団法人日本病理学会事務局 〒113-0034 東京都文京区湯島1-2-5聖堂前ビル7階
封筒に「病理診断特別講演推薦書式在中」と明記の上、書留等にてお送り下さい。
推薦締め切り:
平成28年8月31日(消印有効)
選考:
担当者平成28年秋の学術委員会において厳正・公明に選考し、同年11月の理事会審議にて決定、同総会にて発表いたします。
本件につきましてご質問がありましたら、日本病理学会事務局または学術委員長までお問い合せください。
日本病理学会事務局:TEL 03-6206-9070 FAX 03-6206-9077 jsp-admin@umin.ac.jp
学術委員長(髙橋雅英):TEL 052-744-2092 mtakaha@med.nagoya-u.ac.jp
つきましては、標記担当者の推薦を受けつけいたします。自薦、他薦はといません。下記の要領にてご推薦をお願いいたします。
病理診断特別講演とは:
「病理診断特別講演」は、特定の疾患や臓器における病理診断に関して、本学会に永年にわたって貢献し、その専門に卓越した経験と見識をもつ本学会員が担当し、担当疾患の病理診断に関して主として解説的に講演する。「病理診断特別講演」担当者には、「病理診断学賞」が授与される。
推薦者:
推薦者は、学術評議員であること。自薦も可とします。他薦では被推薦者の内諾を要します。
推薦書式:
1)下記よりダウンロードした所定の推薦書式に推薦者名、候補者名、略歴、活動・功績、課題名、推薦/申請理由(1000字以内)等を記載したもの。
※書式はWord形式です。全体が適切な形で2ページ以内に収まるよう配慮して下さい。
自薦はこちら 他薦はこちら
2)推薦理由に関する論文・著書業績(20編以内)のリスト
提出先:
一般社団法人日本病理学会事務局 〒113-0034 東京都文京区湯島1-2-5聖堂前ビル7階
封筒に「病理診断特別講演推薦書式在中」と明記の上、書留等にてお送り下さい。
推薦締め切り:
平成28年8月31日(消印有効)
選考:
担当者平成28年秋の学術委員会において厳正・公明に選考し、同年11月の理事会審議にて決定、同総会にて発表いたします。
本件につきましてご質問がありましたら、日本病理学会事務局または学術委員長までお問い合せください。
日本病理学会事務局:TEL 03-6206-9070 FAX 03-6206-9077 jsp-admin@umin.ac.jp
学術委員長(髙橋雅英):TEL 052-744-2092 mtakaha@med.nagoya-u.ac.jp
病理検体取扱いマニュアル
病理診断のために採取された病理検体について、臨床医が病理検体を採取してから病理診断書を受け取るまでの過程には、多くのステップがあり、そのほとんどが手作業で行われているのが現状です。これらのすべてにおいて、ヒューマンエラーによる検体の取り違えを生じるリスクがあります。病理診断は、治療方針を決める重要な診断であるので、そのような間違いはあってはならず、間違いを最小にする努力を日頃より病理関係者は実践しています。しかし、不幸にしてヒューマンエラーによる検体の取り違えやインシデントの発生が報告されているのが現状です。ヒューマンエラーはゼロにはなりませんが、できるだけゼロに近づけるべく、「病理検体取扱いマニュアル」を作成しました。このマニュアルは、病理診断を行ううえで基本となる病理検体の取り扱い、標本作製、診断の過程で推奨される標準的な手順をまとめたものです。バーコード、ICチップ等を用いたコンピューター管理によるトラッキングシステムの導入も検討されていますが、いまだ多くのステップでは、自動化やIT化は困難であり、マニュアルでの対応が必要です。また、検体採取から検体の提出までを担う臨床医との十分な連携、認識の共有も必要です。本マニュアルでは、実際の病理検体取扱い過程の時系列に沿って、推奨される手順と避けるべき手技を示すことで、関与する医師、検査技師、医療従事者に分かりやすく実践可能なように記載しました。また、最初に推奨される手順、避けるべき手順をまとめて記載し、一目で重要なポイントがわかるようにしました。本マニュアルがヒューマンエラーの軽減に役立つことを祈っております。
なお、本マニュアルの作成過程でパブリックコメントを求めたところ、多くの先生方の意見をいただきました。可能な限り、いただいた意見を入れさせていただいております。ご協力賜り、本当にありがとうございました。
本マニュアルを、各々の施設における標準作業手順書作成の参考にしていただれば幸いです。
病理検体取扱いマニュアル(全文)はこちら
病理検体取扱いマニュアル(簡易版)はこちら
なお、本マニュアルの作成過程でパブリックコメントを求めたところ、多くの先生方の意見をいただきました。可能な限り、いただいた意見を入れさせていただいております。ご協力賜り、本当にありがとうございました。
本マニュアルを、各々の施設における標準作業手順書作成の参考にしていただれば幸いです。
病理検体取扱いマニュアル(全文)はこちら
病理検体取扱いマニュアル(簡易版)はこちら
2016年7月16日
病理検体取扱いマニュアル作成委員会
森井英一、佐々木毅、滝野寿、徳永英博
病理検体取扱いマニュアル作成委員会
森井英一、佐々木毅、滝野寿、徳永英博
2016年7月12日
第64回(平成30年度)秋期特別学術集会会長ならびに第108回(平成31年度)学術集会会長の募集について(公募のお知らせ)
学術評議員各位
一般社団法人日本病理学会は、第64回(平成30年度)秋期特別学術集会会長ならびに第108回(平成31年度)学術集会会長を以下のとおり募集いたします。
日本病理学会秋期特別学術集会(秋期特別総会)の会長ならびに学術集会(春期総会)の会長は、定款施行細則の定めるところにより、いずれも理事会が選考し、総会において決定しています。
ここに、第64回(平成30年度)秋期特別学術集会会長ならび第108回(平成31年度)学術集会会長を、下記の要領により募集いたします。
1.応募は自薦であること。
2.応募者は、第64回秋期特別学術集会会長の場合は平成30年11月1日に、また、第108回春期学術集会会長の場合は平成31年4月1日にそれぞれ満65歳以下の日本病理学会学術評議員であること。
3. 第64回(平成30年度)秋期特別学術集会会長の応募は、関東地区以外からの限定とすること
(なお開催地は、会長所属機関と異なる利便性の高い場所を選択することもできる)。
4. 応募者は、日本病理学会学術集会開催要領(別記)の趣旨を踏まえて、所定の用紙に学術集会に対する考え方、学術集会の具体的な実行計画、日本病理学会及び関連学会において近年に行った主要な学術活動等を記載すること。記入に際しては、用紙に適切に収まるよう配慮すること。
5. 応募の締切りは、平成28年9月30日(消印有効)までとすること。
なお、所定用紙の交付または本件についての質問がありましたら、本学会事務局までお問い合わせください。
日本病理学会事務局
E-mail jsp-admin@umin.ac.jp TEL 03-6206-9070
【別記】
日本病理学会学術集会開催要領
本学術集会開催要領は、学術集会改革案(平成18年5月1日決定)の主旨に基づき、国際化への対応を含め、改めて学術集会の開催に係る要領を定めたものである。
「背景」
日本病理学会は「病理学に関する学理及びその応用についての研究の振興とその普及を図り、もって学術の発展と人類の福祉に寄与する」ことを目的としており、学術集会は「病理学に関わる学会員が研究発表と意見交換を通して持続的な後継者の育成をするとともに、病理学に関する最新情報の収集を行う場」として重要な役割を担っている。病理学が対象とする分野は広く、基礎研究においては様々な研究手段や技術を包含するのみならず、病理診断の精度向上は社会的要請として日本病理学会に課せられている。これら多種多様な分野の連結を図り、新たな医学と医療の発展に寄与するとともに、医療の質を担保する専門医制度の運用と会員の医療レベルの向上に努める必要がある。一方、学問・技術の進歩による研究活動の深化と拡散化、業務の拡大や専門化、支部活動の活性化、学会・研究会の増加などにより、学会員の学術集会に求めるところも変化してきている。さらに、若手病理医・研究医の育成、国際化への対応も重要な課題となっている。
「開催要領」
これらの日本病理学会における命題・課題をふまえ、学術集会では「学術研究活動の発表・意見交換」と「診断病理に関する最新情報の収集」を乖離することなく保証し、次に掲げる観点に添って開催する。
(1) 病理学に関わる学会員の学術成果の発表の場を提供し、発表を通して若手研究者・病理医の育成を行う。
(2) 蓄積された完成度の高い研究成果や中堅クラスの研究成果の発表を通して病理医・研究者を育成・刺激する。
(3) 病理診断・専門医に関連する講習会を通じて診断精度の維持・向上と新知識の習得を保証し、病理診断医育成を図るとともに、基礎病理学的研究と診断病理学的知見を結びつける研究の推進と発表を促進する。
(4) 世界への情報発信とアジア・オセアニア地域での病理学の中核を担うために国際化に取り組む。など。
(5) 病理学に興味をもつ医学生を増やすため、学部学生の発表の場を準備するとともに、学部学生の参加に便宜を図る。
「具体的留意事項」
(1) 春期学術集会:春期学術集会の学術プログラムが研究と病理診断などのバランスの取れた内容とするため「病理診断講習会」「分子病理診断講習会」とシンポジウム、ワークショップ、一般発表演題との重なりを少なくする。そのために病理学会の事業である「病理診断講習会」「分子病理診断講習会」については、それぞれ病理診断講習会委員会、研究推進委員会は学会長と密接な連携により、その内容の充実を図る。専門医資格更新に必要な講習会を実施する。「宿題報告」は1会場で行いplenaryとする。
(2) 秋期特別総会:「学術研究賞(A演説)(7-8件)」と「病理診断特別講演(旧:診断シリーズ)(2件)」は1会場で行いplenaryとする。会長は学術委員会と密な連携をとり、「シンポジウム」、「B演説」、「教育講演」、「公募演題」などは、会長の裁量で複数会場で行なうことも可とする。IAP教育セミナーなどとの効果的な連動を考慮する。アジア若手研究者を招聘し発表する場として、インターナショナルポスターセッションを開催する。
(3) 学術集会プログラム統一性の確保:春期学術集会会長および秋期特別総会会長の立候補者は、学術集会プログラムの統一性の確保や類似プログラムの反復・乱立の回避などのため、プログラム内容や企画方針などを応募申請書に明記する。
(4) 国際化への対応:学術集会の国際化を促進するために、英語での参加登録、インターナショナルセッションの設置、日程表の英語版の作成などに努める。
(5) 実際の開催・運営に係る詳細な注意事項は別途定める。
平成26年11月19日 理事会策定
平成27年3月17日 同一部改定
平成28年3月25日 同一部改定
一般社団法人日本病理学会は、第64回(平成30年度)秋期特別学術集会会長ならびに第108回(平成31年度)学術集会会長を以下のとおり募集いたします。
一般社団法人日本病理学会
理事長 深山 正久
理事長 深山 正久
日本病理学会秋期特別学術集会(秋期特別総会)の会長ならびに学術集会(春期総会)の会長は、定款施行細則の定めるところにより、いずれも理事会が選考し、総会において決定しています。
ここに、第64回(平成30年度)秋期特別学術集会会長ならび第108回(平成31年度)学術集会会長を、下記の要領により募集いたします。
記
1.応募は自薦であること。
2.応募者は、第64回秋期特別学術集会会長の場合は平成30年11月1日に、また、第108回春期学術集会会長の場合は平成31年4月1日にそれぞれ満65歳以下の日本病理学会学術評議員であること。
3. 第64回(平成30年度)秋期特別学術集会会長の応募は、関東地区以外からの限定とすること
(なお開催地は、会長所属機関と異なる利便性の高い場所を選択することもできる)。
4. 応募者は、日本病理学会学術集会開催要領(別記)の趣旨を踏まえて、所定の用紙に学術集会に対する考え方、学術集会の具体的な実行計画、日本病理学会及び関連学会において近年に行った主要な学術活動等を記載すること。記入に際しては、用紙に適切に収まるよう配慮すること。
5. 応募の締切りは、平成28年9月30日(消印有効)までとすること。
なお、所定用紙の交付または本件についての質問がありましたら、本学会事務局までお問い合わせください。
日本病理学会事務局
E-mail jsp-admin@umin.ac.jp TEL 03-6206-9070
【別記】
日本病理学会学術集会開催要領
本学術集会開催要領は、学術集会改革案(平成18年5月1日決定)の主旨に基づき、国際化への対応を含め、改めて学術集会の開催に係る要領を定めたものである。
「背景」
日本病理学会は「病理学に関する学理及びその応用についての研究の振興とその普及を図り、もって学術の発展と人類の福祉に寄与する」ことを目的としており、学術集会は「病理学に関わる学会員が研究発表と意見交換を通して持続的な後継者の育成をするとともに、病理学に関する最新情報の収集を行う場」として重要な役割を担っている。病理学が対象とする分野は広く、基礎研究においては様々な研究手段や技術を包含するのみならず、病理診断の精度向上は社会的要請として日本病理学会に課せられている。これら多種多様な分野の連結を図り、新たな医学と医療の発展に寄与するとともに、医療の質を担保する専門医制度の運用と会員の医療レベルの向上に努める必要がある。一方、学問・技術の進歩による研究活動の深化と拡散化、業務の拡大や専門化、支部活動の活性化、学会・研究会の増加などにより、学会員の学術集会に求めるところも変化してきている。さらに、若手病理医・研究医の育成、国際化への対応も重要な課題となっている。
「開催要領」
これらの日本病理学会における命題・課題をふまえ、学術集会では「学術研究活動の発表・意見交換」と「診断病理に関する最新情報の収集」を乖離することなく保証し、次に掲げる観点に添って開催する。
(1) 病理学に関わる学会員の学術成果の発表の場を提供し、発表を通して若手研究者・病理医の育成を行う。
(2) 蓄積された完成度の高い研究成果や中堅クラスの研究成果の発表を通して病理医・研究者を育成・刺激する。
(3) 病理診断・専門医に関連する講習会を通じて診断精度の維持・向上と新知識の習得を保証し、病理診断医育成を図るとともに、基礎病理学的研究と診断病理学的知見を結びつける研究の推進と発表を促進する。
(4) 世界への情報発信とアジア・オセアニア地域での病理学の中核を担うために国際化に取り組む。など。
(5) 病理学に興味をもつ医学生を増やすため、学部学生の発表の場を準備するとともに、学部学生の参加に便宜を図る。
「具体的留意事項」
(1) 春期学術集会:春期学術集会の学術プログラムが研究と病理診断などのバランスの取れた内容とするため「病理診断講習会」「分子病理診断講習会」とシンポジウム、ワークショップ、一般発表演題との重なりを少なくする。そのために病理学会の事業である「病理診断講習会」「分子病理診断講習会」については、それぞれ病理診断講習会委員会、研究推進委員会は学会長と密接な連携により、その内容の充実を図る。専門医資格更新に必要な講習会を実施する。「宿題報告」は1会場で行いplenaryとする。
(2) 秋期特別総会:「学術研究賞(A演説)(7-8件)」と「病理診断特別講演(旧:診断シリーズ)(2件)」は1会場で行いplenaryとする。会長は学術委員会と密な連携をとり、「シンポジウム」、「B演説」、「教育講演」、「公募演題」などは、会長の裁量で複数会場で行なうことも可とする。IAP教育セミナーなどとの効果的な連動を考慮する。アジア若手研究者を招聘し発表する場として、インターナショナルポスターセッションを開催する。
(3) 学術集会プログラム統一性の確保:春期学術集会会長および秋期特別総会会長の立候補者は、学術集会プログラムの統一性の確保や類似プログラムの反復・乱立の回避などのため、プログラム内容や企画方針などを応募申請書に明記する。
(4) 国際化への対応:学術集会の国際化を促進するために、英語での参加登録、インターナショナルセッションの設置、日程表の英語版の作成などに努める。
(5) 実際の開催・運営に係る詳細な注意事項は別途定める。
平成26年11月19日 理事会策定
平成27年3月17日 同一部改定
平成28年3月25日 同一部改定
第107回(平成30年度)日本病理学会総会における宿題報告担当候補者の推薦と、宿題報告の募集について(公募)
第107回(平成30年度)日本病理学会総会における宿題報告担当候補者の推薦について
宿題報告担当者については自薦に加えて学術評議員からの推薦を受けております。下記の要領で、宿題報告担当候補者の推薦をお願いいたします。学術評議員から推薦された候補者については、学術委員長名で推薦されている旨をご本人にお伝えし、応募されることをお勧めいたします。
推薦方法:日本病理学会ホームページよりダウンロードした所定の書式に、被推薦者名、演題名(仮題)、簡単な推薦理由、推薦者名、などを記載のこと。
提出先:〒113-0034 東京都文京区湯島1-2-5 聖堂前ビル7階
一般社団法人日本病理学会事務局
推薦締め切り:平成28年7月31日(消印有効)
本件につきましてご質問がありましたら、日本病理学会事務局または学術委員長までお問い合せください。
日本病理学会事務局:TEL 03-6206-9070 E-mail: jsp-admin@umin.ac.jp
学術委員長(髙橋雅英):TEL 052-744-2092 mtakaha@med.nagoya-u.ac.jp
<書式のダウンロード>
>>WORDはこちら >>PDFはこちら
第107回(平成30年度)総会における宿題報告の募集について(公募)
第107回(平成30年度)日本病理学会における宿題報告を下記の要領により、募集いたします。
1.応募資格:日本病理学会学術評議員(ただし昭和27年4月1日以降生まれの者)
2.募集人員:3名
3.提出書類:
・日本病理学会ホームページよりダウンロードした所定の書式に、応募者名、演題名、選考用抄録(1,100字以内)などを記載のこと。ダウンロードできない場合は、日本病理学会事務局まで請求のこと。
・講演内容に直接関係のある自著論文50編以内の一覧
・代表的な自著論文10編以内の別刷
4.提出先:〒113-0034 東京都文京区湯島1-2-5 聖堂前ビル7階
一般社団法人日本病理学会事務局 「宿題報告応募抄録」と明記し、書留郵便等で
お送りください。
5.締め切り:平成28年8月31日(消印有効)
なお、第107回日本病理学会における宿題報告担当者は、平成28年秋の学術委員会において厳正・公明に選考し、同年11月の理事会審議にて決定いたします。また、担当者には"Pathology International"への総説論文の執筆、発表抄録の日・英両言語での作成、「病理学の研究でわかること」の原稿作成をお願いすることをご承知おき下さい。
本件につきましてご質問がありましたら、日本病理学会事務局または学術委員長までお問い合せください。
日本病理学会事務局:TEL 03-6206-9070 E-mail: jsp-admin@umin.ac.jp
学術委員長(髙橋雅英):TEL 052-744-2092 mtakaha@med.nagoya-u.ac.jp
<書式のダウンロード>
>>WORDはこちら >>PDFはこちら
第100回ドイツ病理学会への本学会員招聘派遣報告
日本病理学会の日独交流事業の一環としてこの度、笹野公伸理事、都築豊徳学術評議員の2名が第100回ドイツ病理学会に参加した。学会は2016年6月22日から24日の期間、Berlin、Alexander Platzに隣接したBerlin Congress Center において開催された(写真1)。今回の学会会長であるAachen大学Knüchel-Clarke教授(写真2)の専門が泌尿器病理であることから都築学術評議員が、笹野理事は長年にわたる日独病理学会交流に対する貢献と内分泌病理関連の国際シンポジウムの演者として招聘された。
ホテルに到着すると、部屋にドイツ病理学会のロゴをあしらったお菓子と、Knüchel-Clarke教授直筆の手紙が置いてあり、細やかな心遣いに感激した(写真3)。日本の病理学会に比較して、学会場はかなりこぢんまりとしており、参加者及び発表数も比較的少ないと感じられた(写真4)。Keynote lectureは4演題で、3演題はドイツ以外の国の講演者であった。一般演題は、口演、ポスター口頭発表はほとんどドイツ語で行われたが、ポスターの大半は英語を使用していた。演題数は少ないものの、発表された相当数は多施設、しかも複数国にまたがる症例検討であることに非常に驚かされた。複数のドイツ人参加者にその背景を伺った所、ドイツではresidentもしくはfellowship終了後、多くの若手研究者は海外(欧州内もしくは米国)に留学し、そこで国際的な人間関係を構築するとのことであった。更には帰国後もそれらの施設と関係を持ち、それにより大規模な多施設共同研究が行われているとのことであった。日本病理学会もこれにならって、若手研究者の諸国との交流を活発化し、国際化の仲間入りを推進する必要があると思われた。
学会初日の夕方に、学会場内で100周年記念行事が行われた。学会2日目の夕方に、会長招宴がBerlin Museum of Medical History of the Charité で行われた。同場所はVirchowがベルリンで実際に講義をした施設で、病理関係の歴史的な資料が供覧されている博物館である。第二次世界大戦の際の空爆で屋根が破壊され、内部も炎上したのだが、歴史的建造物として再建されたとのことである。部屋の壁にはVirchowが実際に講義を行った写真が掲げてあった(写真5)。会長招宴に中国病理学会からの参加者も見えたので話を伺った所、中国病理学会は毎年多数の海外研究者の招聘を行い、急速に国際化を進めている実情を教えて頂いた。学会3日目に笹野理事と都築評議員が講演を行った。笹野理事の演題名は Molecular pathology update of adrenocortical neoplasms in 2016で、WHOの改訂を踏まえ、原発性アルドステロン症で報告されているsomatic mutationのKCNJ5 mutationsの意義及び副腎皮質癌におけるmolecular profilingの最近の知見を講演した。都築学術評議員の演題名はGleason grading system, intraductal carcinoma of the prostate, and beyond: What is the most predictive pathological factor of patient outcome.で、ISUP2014で提唱された新しいGleason grading systemの解説及び予後因子として近年注目されているintraductal carcinoma of the prostateの臨床病理学的意義を示した(写真6)。2つの発表とも非常に好評で、多くの質疑応答がなされた。
ドイツ病理学会では国際化が非常に進んでいることが今回の参加で実感された。今後の日本病理学会の発展を考える上で、より一層の国際化を進める必要性が痛感された。

写真1:学会会場であるBerlin Congress Center

写真2:学会会長Knüchel-Clarke教授と都築評議員

写真3:学会ロゴをあしらったお菓子とKnüchel-Clarke教授からの手紙
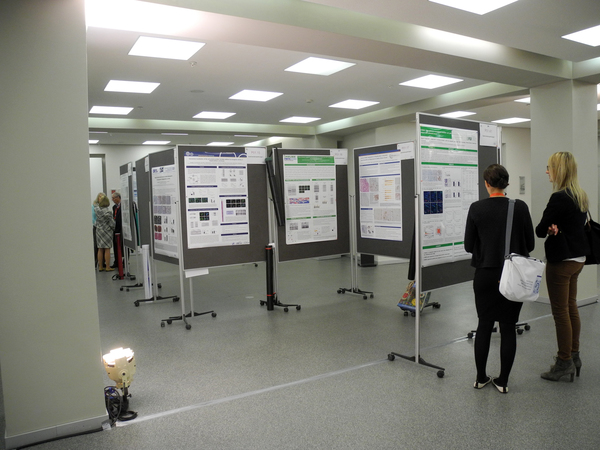
写真4:学会内ポスター会場

写真5:会長招宴会場の壁面に掲げてあるVirchowの講義風景

写真6:発表風景(都築評議員)
文責
都築豊徳 (愛知医科大学 病院病理部)
笹野公伸 (東北大学 病理診断学分野)
ホテルに到着すると、部屋にドイツ病理学会のロゴをあしらったお菓子と、Knüchel-Clarke教授直筆の手紙が置いてあり、細やかな心遣いに感激した(写真3)。日本の病理学会に比較して、学会場はかなりこぢんまりとしており、参加者及び発表数も比較的少ないと感じられた(写真4)。Keynote lectureは4演題で、3演題はドイツ以外の国の講演者であった。一般演題は、口演、ポスター口頭発表はほとんどドイツ語で行われたが、ポスターの大半は英語を使用していた。演題数は少ないものの、発表された相当数は多施設、しかも複数国にまたがる症例検討であることに非常に驚かされた。複数のドイツ人参加者にその背景を伺った所、ドイツではresidentもしくはfellowship終了後、多くの若手研究者は海外(欧州内もしくは米国)に留学し、そこで国際的な人間関係を構築するとのことであった。更には帰国後もそれらの施設と関係を持ち、それにより大規模な多施設共同研究が行われているとのことであった。日本病理学会もこれにならって、若手研究者の諸国との交流を活発化し、国際化の仲間入りを推進する必要があると思われた。
学会初日の夕方に、学会場内で100周年記念行事が行われた。学会2日目の夕方に、会長招宴がBerlin Museum of Medical History of the Charité で行われた。同場所はVirchowがベルリンで実際に講義をした施設で、病理関係の歴史的な資料が供覧されている博物館である。第二次世界大戦の際の空爆で屋根が破壊され、内部も炎上したのだが、歴史的建造物として再建されたとのことである。部屋の壁にはVirchowが実際に講義を行った写真が掲げてあった(写真5)。会長招宴に中国病理学会からの参加者も見えたので話を伺った所、中国病理学会は毎年多数の海外研究者の招聘を行い、急速に国際化を進めている実情を教えて頂いた。学会3日目に笹野理事と都築評議員が講演を行った。笹野理事の演題名は Molecular pathology update of adrenocortical neoplasms in 2016で、WHOの改訂を踏まえ、原発性アルドステロン症で報告されているsomatic mutationのKCNJ5 mutationsの意義及び副腎皮質癌におけるmolecular profilingの最近の知見を講演した。都築学術評議員の演題名はGleason grading system, intraductal carcinoma of the prostate, and beyond: What is the most predictive pathological factor of patient outcome.で、ISUP2014で提唱された新しいGleason grading systemの解説及び予後因子として近年注目されているintraductal carcinoma of the prostateの臨床病理学的意義を示した(写真6)。2つの発表とも非常に好評で、多くの質疑応答がなされた。
ドイツ病理学会では国際化が非常に進んでいることが今回の参加で実感された。今後の日本病理学会の発展を考える上で、より一層の国際化を進める必要性が痛感された。

写真1:学会会場であるBerlin Congress Center

写真2:学会会長Knüchel-Clarke教授と都築評議員

写真3:学会ロゴをあしらったお菓子とKnüchel-Clarke教授からの手紙
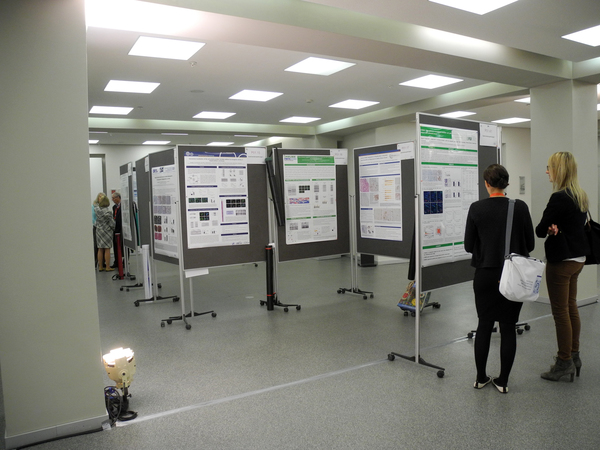
写真4:学会内ポスター会場

写真5:会長招宴会場の壁面に掲げてあるVirchowの講義風景

写真6:発表風景(都築評議員)
文責
都築豊徳 (愛知医科大学 病院病理部)
笹野公伸 (東北大学 病理診断学分野)